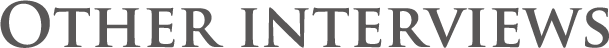あなたのお仕事について具体的に教えてください。
介護ロボット・センサーの開発・販売を手がけるabaという会社を2011年より経営しています。19年に、においセンサーで排泄を検知する「排泄センサーHelppad(ヘルプパッド)」を製品化しました。現在、特養や老健、有料老人ホームなどの介護事業所を中心に病院などでも導入が進んでいます。
この仕事を始めたきっかけを教えてください。
私の両親は飲食店を経営していて多忙だったこともあり、祖母が親代わりとして私を育ててくれました。しかし、その祖母が鬱病となり「死にたい」などの言葉を毎日発するようになりました。私は、それに対して「何かしてあげなくては」と思いつつ、何をしていいかわからず、祖母のことが嫌で自分の部屋に閉じこもってしまっていました。自分自身は何もできませんでしたが「家族の介護をしている人は大変な思いをしている。何か役にたちたい」と感じました。また、「これまでのように人が人を支援する仕組みだと、いつか社会全体が疲弊してしまうのではないか」とも実感しました。
高校生のときに介護ロボットの存在を知り、その開発に携わりたいと思うようになりました。「介護ロボットのことを学ぶなら、千葉工業大学の富山健教授がいいだろう」と周囲の人に勧められて千葉工業大学に進みました。当初は「どこかの企業と介護ロボットの共同開発をして、その経験・実績が就職活動のネタになればいい」程度で研究を始めましたが、在学中に東日本大震災が発生して、私自身も企業も研究・開発体制に大きな影響がでました。そこで「共同研究が無理なら、自分で会社を作ろう」と考え、大学4年生のときに起業をしました。
排泄をテーマにしたのは、研究者として介護現場スタッフと関わったときに「オムツを開けずに中が見たい」を言われたことからです。オムツをされること自体が本人にとっては恥ずかしいことですが、排泄をしていないのにオムツを開けて中を確認されることはさらに恥ずかしいでしょう。逆に排泄があってもすぐにスタッフが確認できなければ、本人は不快な思いをすることになります。センサーで排泄をすぐに検知できれば、そうした問題がなくなりますし、データを蓄積すればその人の排泄のタイミングがわかりますので、適切なタイミングでのトイレ誘導が可能となり、オムツ外しにつながります。
あなたの強みは何ですか?
周囲の人をどんどん巻き込み、支援者や協力者、理解者を増やしていく力です。私は子どものころから「自分が理解できず、納得できないことは全くやらないが、理解・納得でき、やると決めたことは徹底してやる」という性格でした。今でも「この人の持つ知識や技術は当社にとって役に立つ」と判断すれば、どれだけ大変な思いをしてでも接触し、協力をお願いします。ある人は、それを「熱意ではなく執念のレベルだ」と表現しました。また、私のそうした姿を見て全く知らなかった人が協力を申し出てくることもあります。
あなたの使命とは何ですか?
介護現場で働く方々がやりたいケアを実現できるツールをどんどん作り続け、それを普及させることです。
当社を含め、介護ロボット・ICT機器を研究・開発している会社は多数ありますが、現場へのロボット・ICT機器の普及はあまり進んでいない実感があります。それには、研究・開発側が現場を知らず、ニーズに合致していない製品を供給しているという面がありますが、それ以上に介護現場の特殊な事情があると思います。例えば特養や介護付有料老人ホームなど24時間365日休むことなく稼働している現場では、全ての介護スタッフが一堂に会して、ロボットや機器の導入に関する会議を行い、意思の統一を図ることが極めて困難です。また、好ましいことではありませんが、職種や職歴による職場内のヒエラルキーも存在し、それが意思統一の妨げになることがあります。
当社では、介護業界向けにビジネスをしたい企業を対象に、介護業界のこうした特殊な事情を説明したり、介護事業者に対するヒアリングに同行し、ときにはファシリテーターを務めたりする新事業「aba lab」を21年2月より開始しています。介護はその人の生活全般を支えるものであり、世の中のほとんどの企業にとって関わる余地があると言えます。当社のこうした取り組みによって、多くの会社が介護業界に関わりをもち、介護現場で働く人たちや家族の介護をしている人たちが笑顔になれる社会を作りたいと考えています。
最後にあなたのこれからの夢を聞かせてください。
ドラえもんの秘密道具に「お医者さんカバン」というものがあります。未来の子どもたちがお医者さんごっこをするためのおもちゃなのですが、聴診器やレントゲンでその人を診察でき、その場で症状に応じた特効薬が作れる機械です。これの介護版をつくるのが夢です。介護を必要とする人の心身の状態には個人差があります。本来ならば「お医者さんカバン」のようにフルオーダーでその人にあった介護ロボット・機器を作れればいいのですが、それは価格などの面で非現実的な話です。一方でマスカスタマイゼーションというセミオーダー方式を採用することで、個別のニーズに応じた対応と生産性の両方を確保できます。
私が目指すのは現代のフローレンス・ナイチンゲールです。近代看護の祖と言われる彼女は、科学やテクノロジーに関する知識・造詣も深く、現在のナースコールの原理を発明しています。現場にテクノロジーが上手に介入することで、スキルや経験が無くても質が高く安全な介護が行えるようになります。それは結果的に社会全体の介護力をあげ、介護人材不足の解消など様々な形で社会にメリットをもたらすことになると思います。