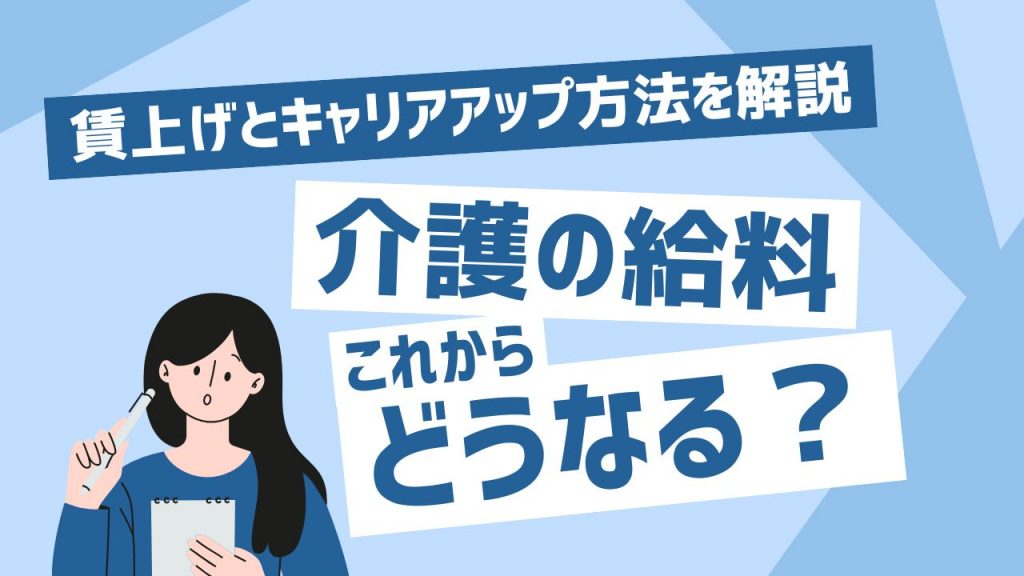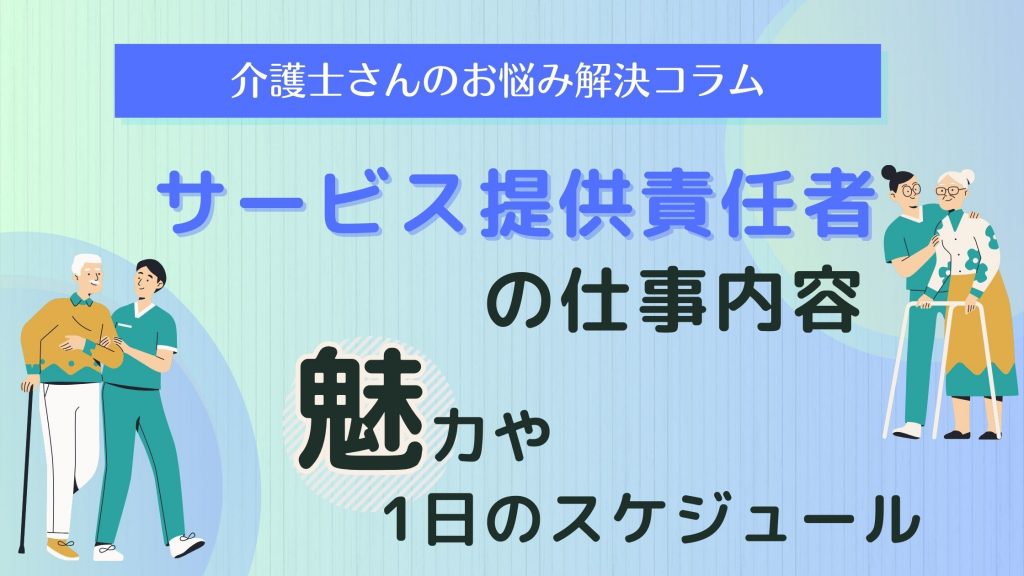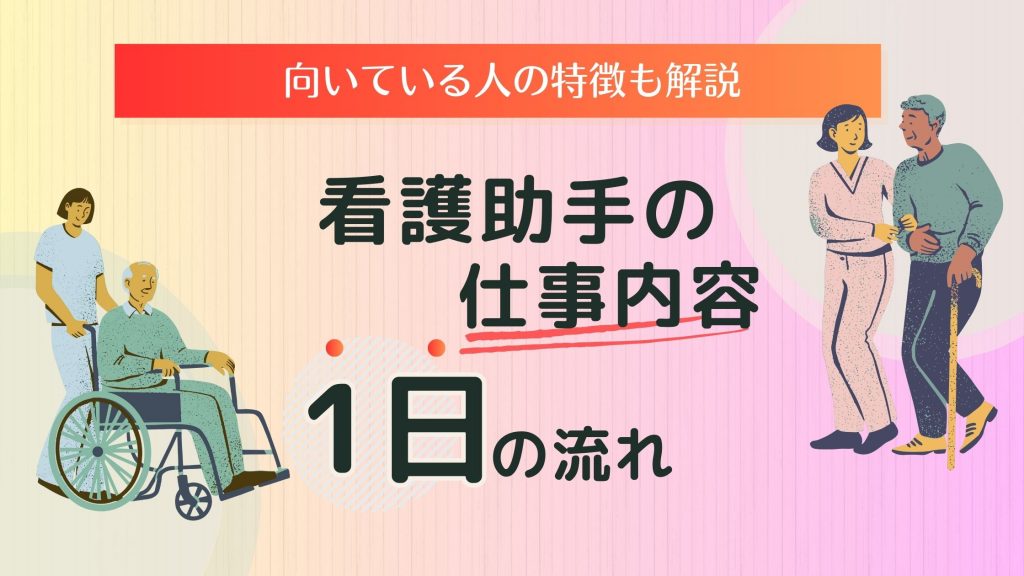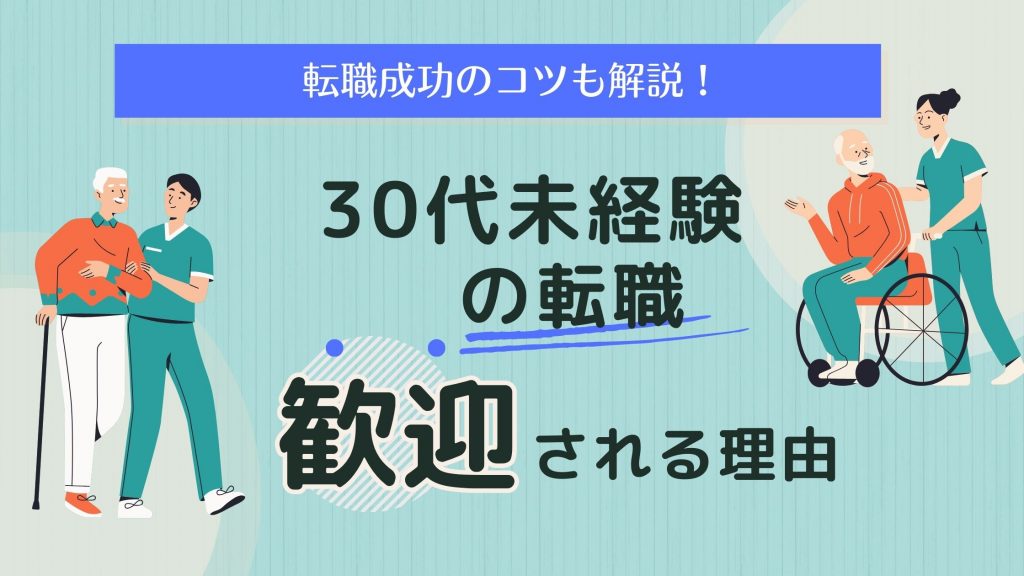お祝い金禁止!有料職業紹介業 重要改定とは
2021/08/12
最終更新日:2021/12/29
介護の求人情報を出す際、就職祝い金○万円などと行ったキャッチコピーが原則として禁止になったことをご存知でしたか?
有料職業紹介事業者が求職者を集めるための施策としてこれまで活用されてきた「お祝い金」ですが、なぜ禁止となったのでしょうか?そこには制度を悪用した紹介会社の存在があるのです。今回は、お祝い金表記禁止の背景とともに、優良な紹介会社の選び方をご説明いたします。
有料職業紹介事業の運営における基本的指針
そもそも有料職業紹介事業者(以下 紹介会社)とはどのような存在なのでしょう。起源は古く、日本では江戸時代のことからすでに似たようなことをする業者が存在したそうです。しかし、当時は業者がたくさんの利益を得る一方、労働者には過酷な環境が強いられていました。やがて労働者の権利を守る機運の高まりとともに、紹介会社の運営にも様々な規制がかけられるようになったそうです。
では現在では、どのような規制・運営指針が定められているのでしょうか?紹介会社を選ぶ際の材料にもなりますのでご確認ください。
多くの求職者に適合する幅広い求人紹介
転職活動をする際、自身のスキルや適正・希望に合った求人を探す難しさを感じることはありませんか?多くの企業の中から自分にあった求人を探すことは決して容易ではありません。そこで便利なのが紹介会社を利用する方法です。求職者の希望・適正などを元にぴったりの求人を紹介してくれます。求職者が自身では見つけることができなかった求人や、気づくことのできなかった選択肢を示すことで可能性を広げるということが紹介会社の存在意義とも言えますね。
個人情報の適切な取り扱い
紹介会社は、その職種の性格上様々な情報を扱います。求職者の個人情報もそのうちの一つです。氏名や生年月日のみならず、収入や住所、職歴・学歴などは万が一流出した場合悪用されかねません。そのため厳重な取り扱いが求められます。一方で求人に関する適切な情報提供も大切です。賃金や待遇、福利厚生や業務内容などを的確に求職者に伝えなくては、転職時の大事な判断に大きく影響しますね。
就業を促すために故意に事実よりも好条件に見せるようなことはあってはなりません。このように情報の取り扱いには特に細かく規制が設けられているのです。
差別的な扱いの禁止
個人の信条や出身地、国籍、人種、宗教による差別は紹介会社だけでなく、憲法で禁止されているのをご存知でしたか?他にも「あなたは女性 / 男性だから」「○歳だから」「デイサービスしか経験がないから」など、性別や年齢、これまでの経験だけでこのように言われてしまうとどのように思うでしょうか。こういったことも差別的な取り扱いとして規制対象になる可能性もあります。紹介会社の存在意義、「求職者の可能性を広げる」ということに照らし合わせても、差別的な取り扱いは規制の対象です。
求職者へのお祝い金禁止!
上記で紹介したように過去の事例などから求職者を守るための規制が設けられてきましたが、令和3年4月1日の法改定により求職者へのお祝い金制度が禁止されました。こうなった背景にはお祝い金を悪用した紹介会社の存在があります。
紹介会社は紹介した人材が一定期間(3ヶ月程)以内に退職してしまった場合、紹介した法人から受け取った手数料の一部を返金する義務があります。裏を返すと一定期間経過すれば手数料の返金は不要なのです。なので、紹介した人材に対して一定期間が経過した後「お祝い金を出すので、また転職しませんか?」とそそのかす紹介会社が現れたのです。
仮に年収300万円の人材を紹介した手数料が20%だった場合で想定してみます。法人から受け取る手数料は300万円の20%=60万円ですので、仮にお祝い金10万円を求職者に支払っても、紹介会社には50万円残るのです。
短期間のうちに転職を繰り返せば、紹介会社はそれだけ稼げるのです。これでは本来の紹介会社の枠割りから大きくかけ離れてしまいます。そこで今回のお祝い金禁止に繋がったのです。
いまだに「お祝い金」を強調している会社には注意!
禁止されたとは言え、現在全国に2万社以上もある紹介会社全部を調査することも難しいのが現実です。中には現在も「お祝い金○万円!」などと強調している紹介会社もあるかもしれません。求職者の中には「お祝い金があったほうが助かる」と考える人もいるかもしれません。しかし法律で禁止されているお祝い金を強調しているということは、法律を軽視する企業体質だと見ることができます。「お祝い金」以外にも法律や規制に反した運営をしている可能性も考えられますね。転職後に後悔しないためにも、今現在も「お祝い金」を強調している企業には注意する必要がありそうですね。
では一体、何を基準に紹介会社を選ぶべきなのでしょうか?
ポイントは2つです。
ポイント①職業紹介優良事業者か否か
法律や規則を守り健全な運営をしている紹介会社には国から「職業紹介優良事業者」に認定されるのをご存知でしたか?また、医療・介護・保育分野においては「適合宣言紹介事業者」という認定制度もあります。どちらの認定も、求職者に対しても法人に対しても適切なサービスを提供しているという証明になります。「人材サービス総合サイト」にて居住地や希望する職種などからの検索も可能なので、一度検索してみるのはいかがでしょうか?
ポイント②紹介会社の質の次は担当者の質をチェック
良質な転職活動ができるか否かは担当者に左右される部分も大きいでしょう。いきなり求人を勧めてくる担当者もいれば、ヒアリングに時間をかける担当者もいます。求職者が理想とする担当者は「こちらの希望を汲みつつも、自身では気づかない、見つけることのできなかった可能性を示してくれる」ような人ではないでしょうか?
特養を志望していたが希望する働き方やキャリアを活かせるのは有料老人ホームだった」「訪問介護の経験しかなかったが、デイサービスにも興味が湧いた」など、一人で転職活動をしているときよりも視野を広げられることが、紹介会社を利用するメリットですね。
現実には担当者を選ぶことのできる紹介会社は少ないでしょう。複数の紹介会社に問い合わせ、面談の中で自分につく担当者を基準に紹介会社を絞り込むと、満足のいく転職活動につなげられるのではないでしょうか。
法改正に伴う「お祝い金」の禁止や紹介会社の選び方についてお話ししました。人材不足が特に深刻化している介護業界。応募すれば高確率で採用される状況とも言えます。しかし入職してから「想像と違ったからまたすぐに転職」したのでは、自分のキャリアのマイナスになってしまうこともありますので、まずは信頼できる紹介会社を選ぶことが大切です。