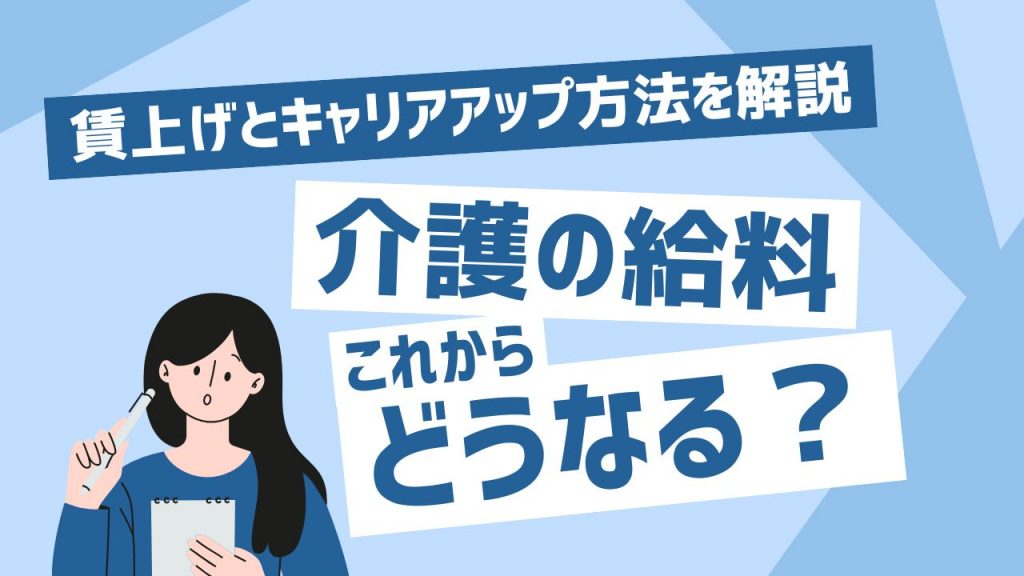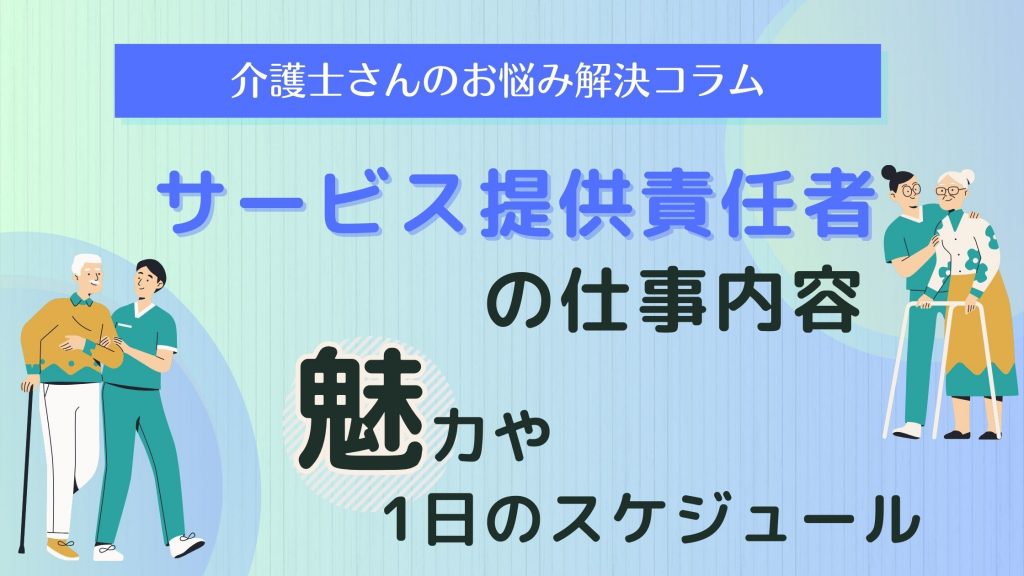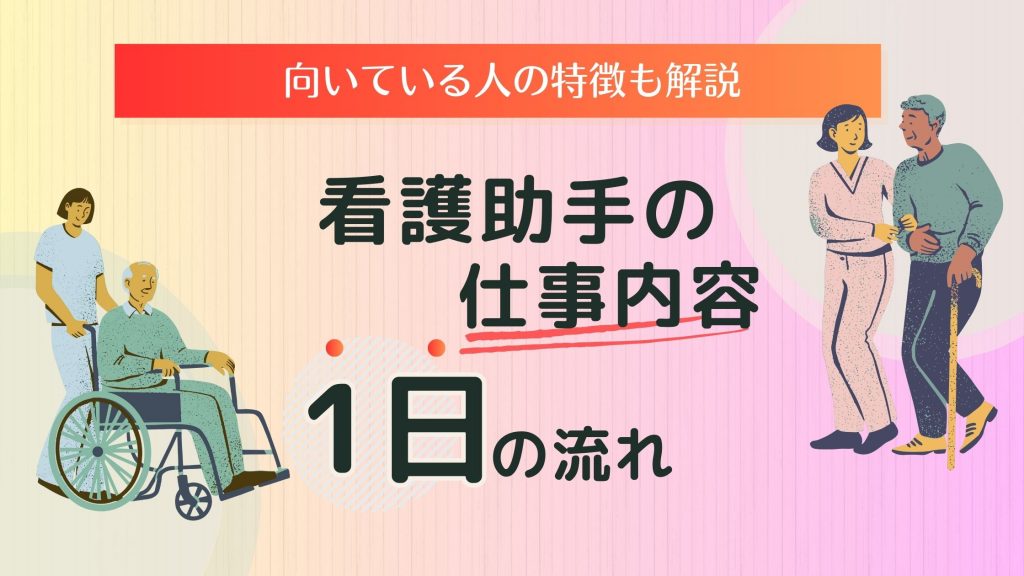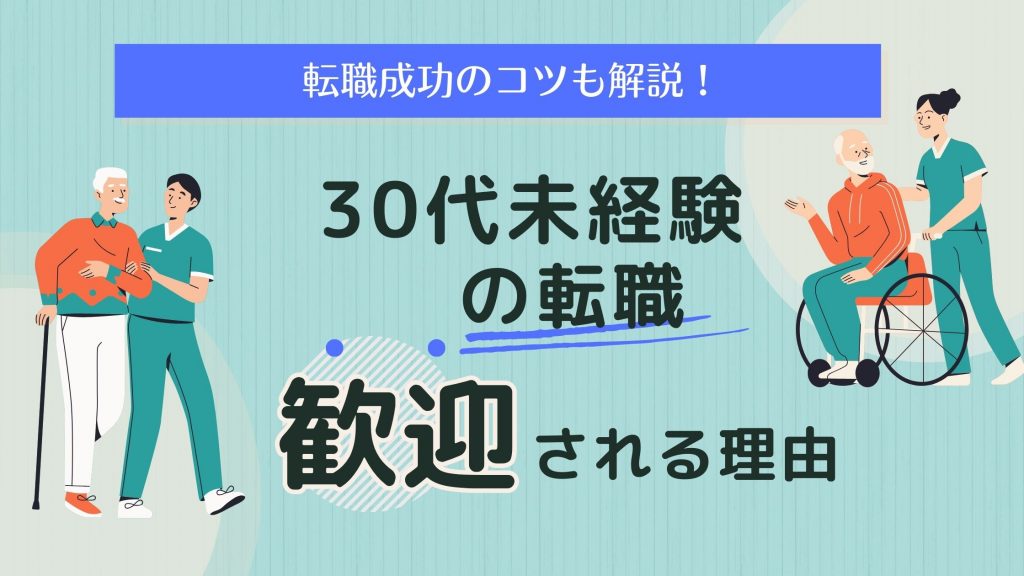【保健師のお仕事】 地域包括支援センター
2021/08/13
最終更新日:2021/12/29
行政や一般企業、病院や学校など、保健師の勤務先は様々です。それぞれに異なる特徴があり、就職先に選ぶ際のメリットや魅力も違ってきます。数ある就職先の選択肢の中に、地域包括支援センターがあるのをご存知ですか?
行政や一般企業に比べると保健師の就職先としての認知度はさほど高くはありません。
では地域包括支援センターとはどのような施設なのでしょうか?そこで保健師は実際に何を担当し、どのような業務があるのか、他の勤務先との違いや就職するメリットなどについて紹介いたします!
地域包括支援センターってどんなところ?
地域包括支援センターとは、高齢者の方が抱える様々な問題を、福祉・介護。医療・保険などの面から地域で総合的に支援するための相談窓口です。
日本では現在、世界でも類を見ない速度で高齢化が進んでいます。地域との関わりはどんどん希薄になってきていますが、一人暮らしの高齢者や認知症患者、要介護認定者を抱える世帯は急増しています。
これまで家族や地域の人が協力しあって高齢者の生活を支えてきましたが、そのシステムだけでは十分なケアが行えないようになってしまっているのです。そのため、法的援助・医療・介護・日常生活の支援・住宅の確保・などを地域で包括的にサポートしていく必要が出てきたため作られたのが地域包括支援センター。
高齢者が住み慣れた地域で生活できるよう、専門的な知識を持った職員が日常生活支援や介護予防サービス・保健福祉サービスについての相談に応じてくれます。また、介護保険の申請窓口を担っているのも地域包括支援センターです。
現在国は、2025年(団塊の世代が75歳以上になる頃)を目処に、高齢者の方が住み慣れた地域で今まで通り暮らしていけるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援のサービスを一体で提供することのできる「地域包括ケアシステム」の整備を目指しているのです。
また、高齢者だけでなく虐待問題を抱えている家庭などもあり、対策が必要とされています。
このように地域の人たちが安心して暮らし続けられるよう、それぞれのケア施設やサービス機関と、それを必要としている人とを結び付け、活動を支援しているのが地域包括支援センターです。
行政直営のものと、行政からの委託を受けた法人が運営を行っているものの2種類あり、委託業務として運営している地域包括支援センターの方が数が多くなっています。提供されているサービスは変わりなく、担当エリアの住民の心身の健康を守り、健全で安心して過ごせる暮らしを継続して行くためのサポートを行っています。
地域包括支援センターで保健師は何をしている?
それでは地域包括支援センターで保健師が日々どのような業務を行っているのかについてご紹介します。
介護予防 ケアマネジメント
支援が必要だという認定を受けた人や、これから支援や介護が必要となる可能性が高い人を対象に、身体状況や病状の悪化を防ぎ、自立した生活がより長く継続できるよう介護予防の支援を行います。地域の高齢者やそのご家族様からの介護サービスの相談に乗ったり、要望に応じてケアマネージャーと連携を取りながらケアプランの作成するのも保健師の仕事です。
健康診断の受診促進
地域住民や地域の関係機関と連携して、健康診断の受診を促し、健康を守ります。
教室を企画・主催
地域の高齢者やご家族を対象に健康づくり教室や口腔ケア教室の開催、教室の紹介を行い、地域住民の疾患予防の意識増進を図ります。
家庭訪問
高齢者宅の自宅を訪問し、体調管理や日々の生活についてなど相談に乗ります。
来訪者の相談対応
地域包括支援センターに相談しに訪れた方のお話を伺い、内容に応じて対応します。
地域包括支援センターを訪れる方の悩みは1つとは限りません。例えば、最近退院してきた一人暮らしの高齢者がいるとすれば、退院後も食欲が戻らない、一人で身の回りのことをするのが不安・介護支援を受けたい、金銭的にも生活が苦しい、など複数の問題を抱えている場合もあります。
地域包括支援センターでは、食欲の悩みについては保健師がサポート、介護支援についてはケアマネージャーや介護支援サービスと連携を取り、生活の悩みについては社会福祉士が対応する、といったように、複数の専門機関が連携を取り、協力しながら包括的にサポートするための場所なのです。全く何も知らない状態で困ったことになってから自身で各機関に相談してまわるのは大変ですし、受けられるサポートが受けられないといったことも起こりえます。サポートする機関側からみても、各機関がバラバラに支援を行うよりも的確にニーズに沿った支援が円滑に行えるようになります。
高齢者やそのご家族が地域包括支援センターに相談に行くだけで自分が必要とするサポート機関につなげてもらうことができるのです。
地域包括支援センターには経営元が介護施設といった受託施設もたくさんあります。そのような施設に転職した場合、介護業務も手伝わされてしまうのではないか、と不安に思う保健師もいるのではないでしょうか?しかし実際にはきっちりと業務や役割の分担がなされているので保健師が介護業務に関わることはありません。食事介助や入浴介助、着替えの手伝いなども保健師の仕事内容には含まれていないのでご安心ください。
保健師が活躍できる場所!ただ認知度が低い
地域包括ケアを行なっている現場でこれから保健師のニーズはますます高まっていくでしょう。しかし保健師の就職先や転職先としての選択肢として、あまり認知されていないのが現状です。
地域包括支援センターでは、経験が少ない保健師や新卒であっても採用されることが多くあります。未経験でも予防医療に関する講演や企画に関わることもできますし、健康増進に関する相談業務の経験もできますので、キャリア形成という意味では大きなメリットとなりますね。
病院勤めをしていた保健師が地域包括支援センターに転職する際も、医療職の方とのスムーズな連携が求められる仕事なので、慣れるのも早いのではないでしょうか。こなすべき業務内容も明確であり、同じ医療の現場に関わっている周りのスタッフとチームで取り組むことになりますので、「何をしていいかわからない・何から始めればいいの?」といった悩みも心配ありません。
センター内だけでなく外部の機関とも連携をとり協力し、保健師としてのキャリアを築いていくことができます。複数人で業務をこなすため、休暇が取りやすいというメリットもあります。
一般企業に勤める産業保健師は、自身の努力次第で上に上がっていくことができるという大きなメリットがあります。そのためには自分自身で積極的に働きかけ、実績を残し評価を得る必要があります。経験が浅い場合は上に上がっていくことも、そもそも就職することさえ困難な場合もあります。そんな時、地域包括支援センターで経験を積んでから産業保健師を目指すという道もあります。地域包括支援センターでの経験を活かし、より的確なアドバイスや健康推進のための企画をしたり、実行したりすることができるようになります。
今後高齢化社会がますます進んでいく中で、地域包括支援センターでの保健師の重要性がますます高まっていくことがお分りいただけたでしょうか?高齢者の疾病予防や生活のケアに関わり、キャリアを積んで行きたいと考えている方は地域包括支援センターへの就職・転職を検討してみてはいかがでしょうか?