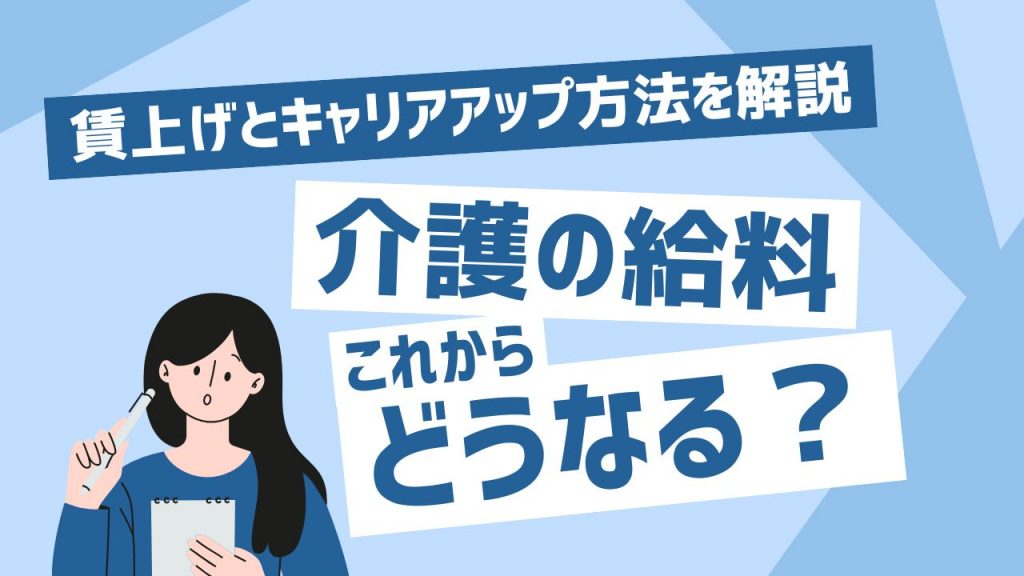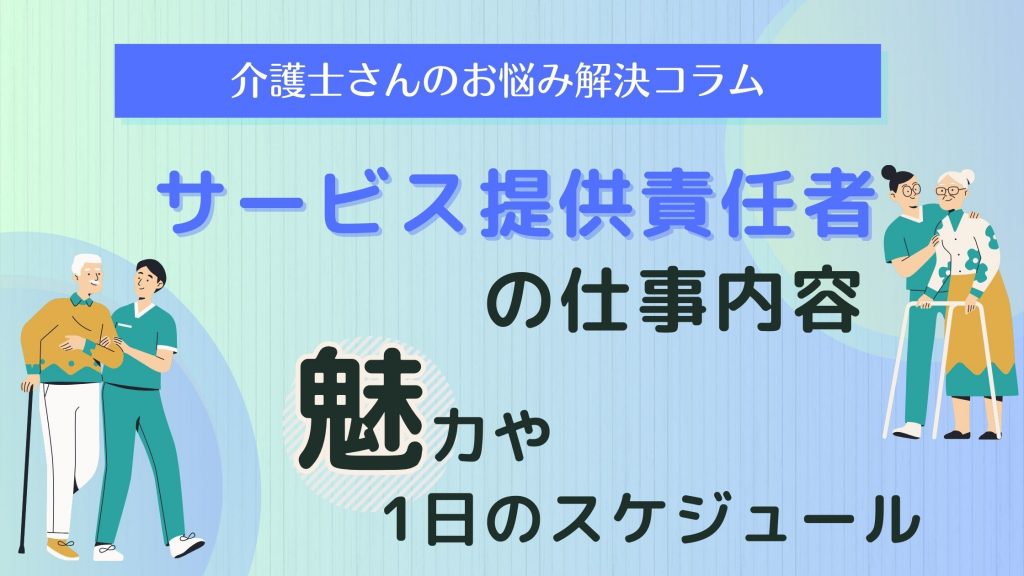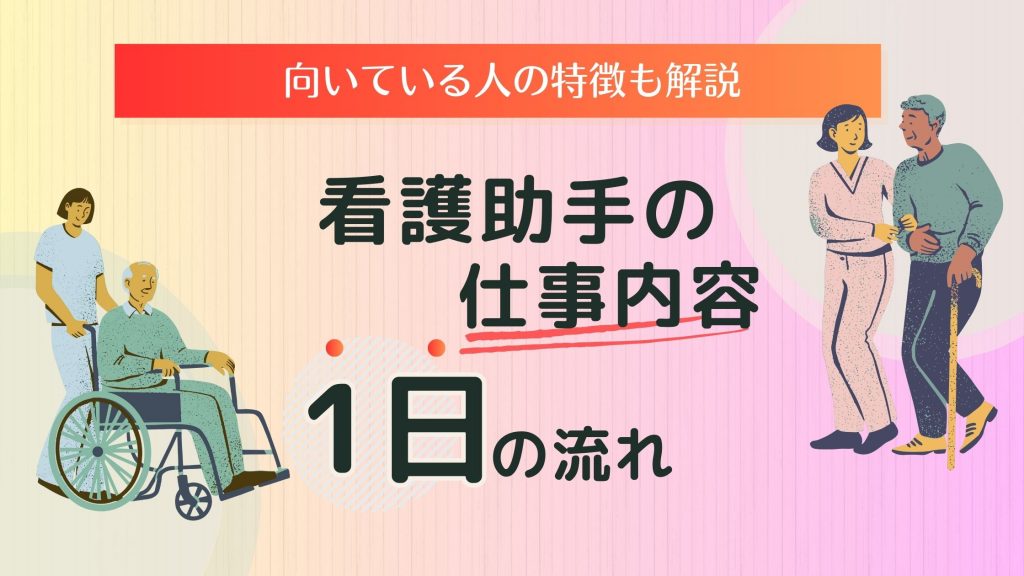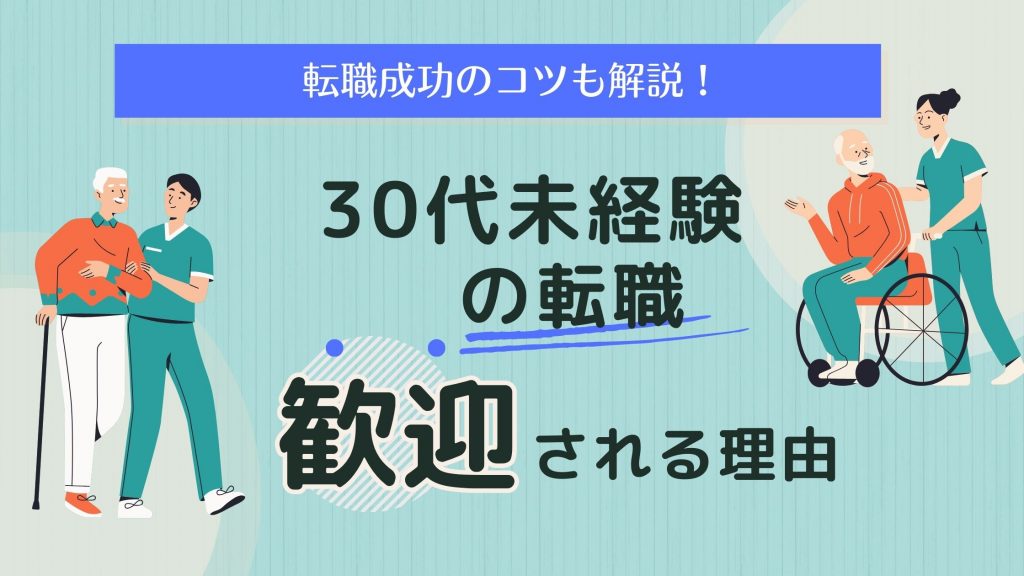高齢者虐待は身近な問題です。防止するには?虐待を起こさない環境とは?
2021/12/24
最終更新日:2021/12/27

高齢者虐待防止法
(定義)
<高齢者>
65歳以上の者
<高齢者虐待>
①養護者による虐待
②養介護施設従事者等による虐待
高齢者虐待の区分とその例
(身体的虐待)
殴る、蹴るなど、身体に外傷を加える行為。または生じる恐れがある。アザが残ったり、出血したりすることもあるが、 痕跡が残らない形で虐待を行っていることもあります。
(心理的虐待)
暴言、侮辱的の言葉を浴びせることや、威圧的な態度、拒否的な対応など、 高齢者に対して精神的に苦痛を与える言動のこと。また、子供扱いして侮辱したり、無視をしたり、意図的に恥をかかせ自尊心を傷つける行為。
(性的虐待)
理由もなく性器に触れる、性的な部位に触れさせるなどの行為。 介護拒否が強いから着脱介助中に上半身を露出したまま放置するなどの行為も性的虐待になります。
(介護放棄「ネグレクト」)
食事を与えず衰弱させるような行為。長時間の放置をして介護を怠ること。または自分自身で食事を食べずに衰弱してしまう場合はセルフネグレクトという場合もある。
(経済的虐待)
高齢者の財産を不当に処分すること、高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
尊厳を傷つける行為は全て虐待といえます。そして、認知症のある人は虐待を受ける割合が高くなっています。また、虐待にはストレスが大きな要因として挙げられています。それでは、介護施設で不適切なケアとはどのようなことが考えられるでしょうか?
・食事介助の関係でゆっくり時間を取れないなので食事を無理やり食べさせる
・「〇〇ちゃん、〇〇ちゃん」と声掛けする
・「よくできまちたね」と子供相手のような声掛けをする
・「同じことを何度もさせないでよ」と言って怒る
・「〇〇さんは、耳が遠いからどうせ聞こえないし、認知症も進行しているので〇〇しても意味ないよ」
・「〇〇さん、車椅子から立ち上がらないで!!」と動けないようにテーブルに近づけて動けないようにする
上のようなことやそれに近い行動に対して、全く覚えがない方はいるでしょうか。
あなたにぴったりのお仕事探しはプロに相談してみよう

転職サイトでは、新しい転職先や働き方など、コンサルタントが無料で提案してくれます。今の職場が自分に合わないと悩んでいるのであれば、まずは相談してみるのがおすすめです。
介護の基本はやはり関わり方

介護現場は確かに忙しく、認知症の周辺症状等で、いろいろなことがあるでしょう。ですが、ご利用者様一人一人としっかりコミュニケーションが成立すれば、ゼロとはいいませんが、介護負担軽減に繋がります。
介護の基本はやはり関わり方なのです。
相手の話を心の底から耳を傾けて聞く姿勢「傾聴」
相手の意見を自分のことのように共に感じる「共感」
どのようなことも善悪の区別なく受け入れる「受容」
このどれか一つが上手くいかないと、やはり介護職側からは、「ご利用者様が言うことを聞いてくれない」となってしまいます。それが重なってくるとストレスが溜まってきます。
また、後輩・同僚からの要望や先輩、上司からの指示・要求が上手くいかないとやはりストレスが溜まります。これも虐待へのトリガーの一つかもしれません。介護職員も人間ですので「他者から認められたい」、「普段の仕事を評価してほしい」と考えることは当然なことなので、そのような心の声をしっかり受け止めることも必要なことです。
高齢者になると、社会的役割の喪失、配偶者や身近な人との死別、家族や地域社会との孤立、年金収入だけなどによる経済的な問題など心理社会的要因などからやる気や元気がなくなる方もいます。若い時と違って身体機能も低下することもあります。高血圧などの生活習慣病もあります。
そのような心身状態になれば、人に頼りたくなったり我儘になるようなこともやはりあります。その欲求が家族に常時向けられてしまったら、やはり家族も疲れてしまいます。
また、親など介護が必要になった人をもつ家族には、家族の歴史(関係・恨み・憎しみを含む感情)と、家族だから面倒を見ないといけないという義務感によって葛藤し、苦しむ家族も少なくありません。ストレスが溜まりすぎて限界を超えてしまうと人は不幸な行動(虐待)に出てしまうかもしれないのです。
対処方法ですが、そのようなときは大きく深呼吸するのが良いかもしれません。もう一度自分を落ち着かせる時間を設けることです。また、誰にも相談できない。悩みを聞いてくれない。悩みを共有できないと、物事は悪い方向に進んでしまうかもしれません。自宅で介護されているご家族の方であれば市役所などに相談したり、「虐待通報ダイヤル」で相談もできます。
国や地方でも始まっている法整備

厚生労働省からも「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令」(令和年1月25日厚生労働省令第9号)により、本年4月より、利用者の人権の擁護、虐待防止等の観点から、全ての介護事業者を対象に虐待の防止のための対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修をすること等を義務化(令和6年3月31日までの間、経過措置を設定)となりました。
高齢者虐待については大きな問題と整備が必要だと国も考えていることなのです。個人的な意見にはなりますが、介護現場では利用者様や入居者様による虐待やハラスメントが御家族様によるものも含め、福祉、医療現場では決して少なくない。むしろ、多いのではないかと思っています。
埼玉県の介護初任者研修では、そのようなハラスメントについて講義の対象となっております。その講義を受け採用された介護職は利用者様によるハラスメントの知識を得ているので、そのようなことがあった場合は上司に報告していると考えます。ですがほとんどの上司は介護をしている時にそのような場面にも出会うため「そんなの介護現場では当たり前だろ」の風潮がやはりあります。
ですが、これが介護の仕事続けたくても心や身体が拒否反応して介護から離れてしまう。そのようなことが多ければ介護人材不足の要因の一つになると考えます。
医療現場では、処置をするとき痛くて暴れてしまう。言葉で反撃する患者様もいるでしょう。医師や看護師からすれば業務上ありえることなので、それに対処できるようになるもの。我慢するものと捉えていることもあり、そのような要因から介護現場でもなかなか改善されないのも事実です。
介護士にとって働きやすい職場環境を作ることも大切

私の職場では、職員が入居者から受けたケガはもちろん、看護師が直ぐに処置しますが、例えば「胸を蹴られて痛みが続く」等があるときは直ぐに病院に受診して頂き労災対象とします。また、再発防止のため、担当を変えたり、介助する人数
を増やします。ここで根底なことなのですが、認知症等病気が起こす場合と認知症などなく、頭で理解出来ていても暴力やハラスメントする場合では大きな違いがあります。
認知症などの病気の場合は、上記のような介助方法を変えますが、頭で理解していて悪い事だと解っているのに行っている入居者様ご利用者様には、私は徹底的にお話をして時には注意をして再発防止に務めます。
また、どのような場合でも速やかにご家族様には状況報告いたします。もちろん関わり方が問題でそのような行動か発生することもあるので、先ずは職員にも関わり方に問題なかったかを第一に考えて頂きます。職員間でカンファレンスも行い介護の方法について何度も話し合います。
状況に応じて主治医に相談致します。ご本人やご家族様了解のもと主治医の判断で処方薬の見直しもございます。それでも改善がされない場合は周りの入居者様、利用者様、そして職員の安全を考慮し、アフターフォローも整えてご利用を中止若しくはご退所して頂く場合もございます。
働きやすい職場環境を作ることも管理者の務めの一つです。先ずは管理者がすべての職員と同じ目線にたつことが大切です。時には入浴、排泄、食事などの介助または、夜勤、掃除、洗濯、庭の草むしり。現場職員と同じことをすることは大きな気付きに繋がります。大切なことだと思います。
つづく
この記事を書いた人

加藤 英明
介護福祉士/主任介護支援専門員
社会福祉法人熊谷福祉の里にて、特別養護老人ホームクイーンズビラ桶川副施設長として従事する。介護講師や地域福祉団体『埼玉県央ケア協会』の共同代表として、県央地域を中心に地域福祉向上のため活動中