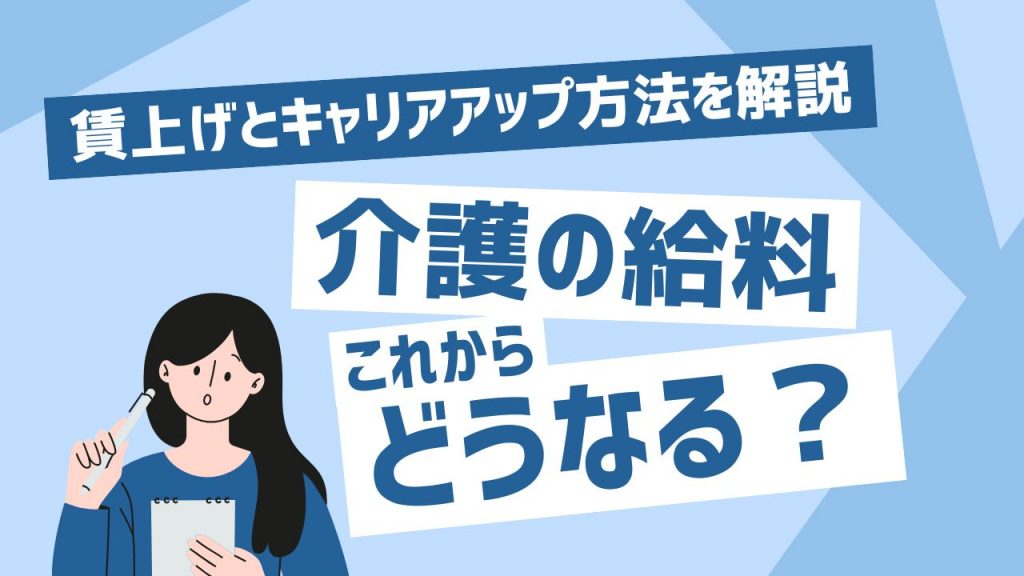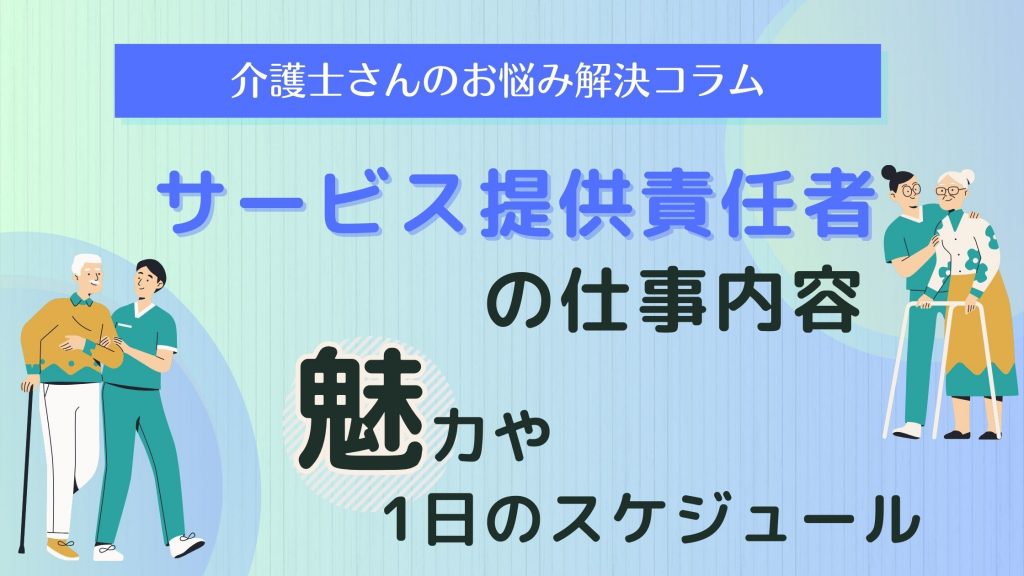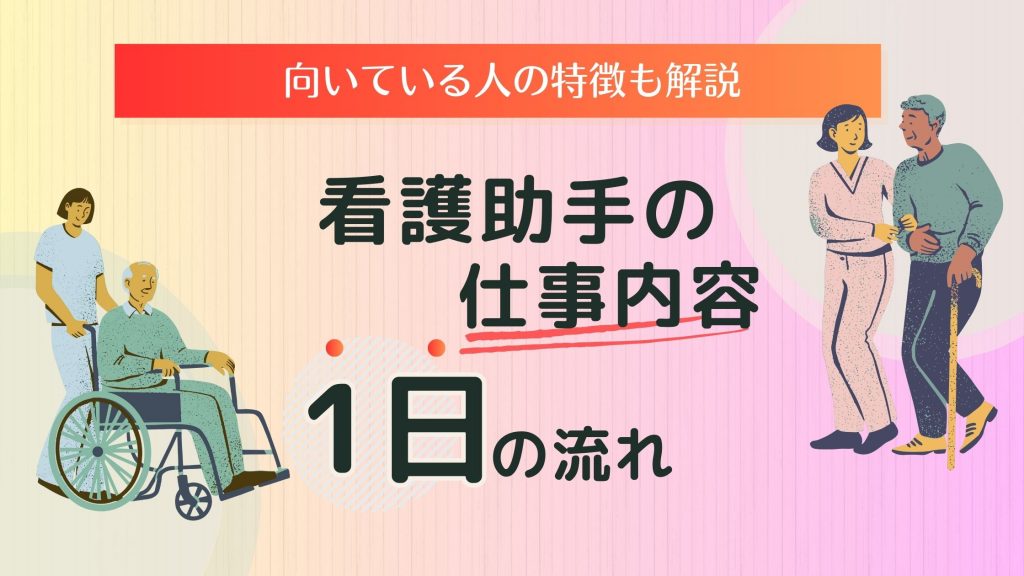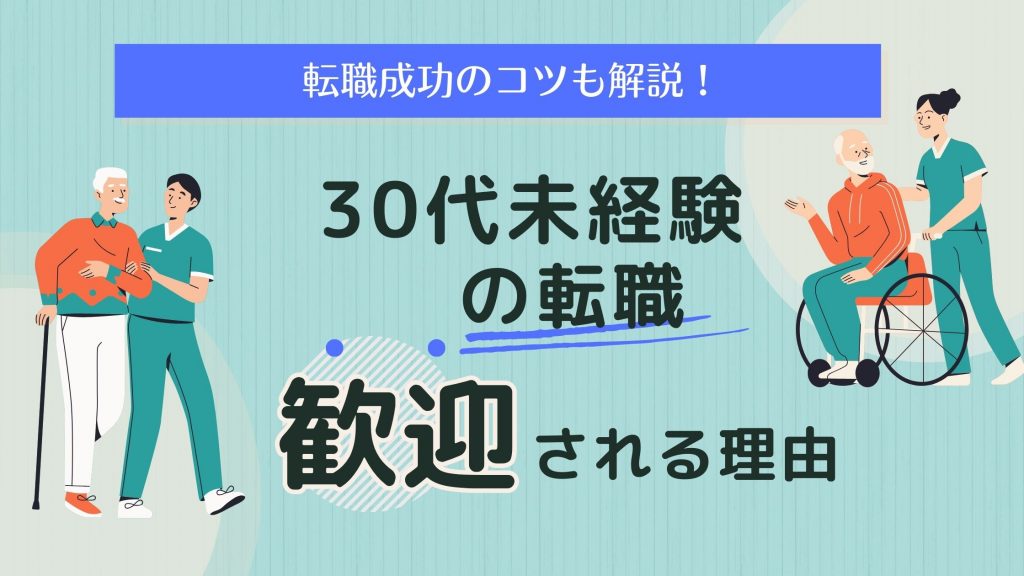介護施設で働く介護士が知っておきたい薬の管理
2022/01/23
最終更新日:2022/02/07
介護職の方々がご活躍される場所は様々です。今回は老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅などの施設でご活躍される介護士の方に向け、お薬の取り扱いの際の注意点やポイントをお伝えしたいと思います。

施設では服薬カレンダーでの管理が一般的
ご施設ごとに多少違いはあると思いますが、一般的には入居者様全員分のお薬を一括して事務所やナースステーションで預かり、管理されているところが多いです。朝・昼・夕・寝る前と1日で4枚の服薬カレンダーを用意して、マスごとに入居者様のお名前を記入し、そこに一包化された薬剤を入れて日にちごとに管理する形が最もポピュラーです。食事の時間になると、カレンダーがリビングに運ばれ、そこでカレンダーから各ご利用者様にお薬を配り、服薬していただくお手伝いをする、という一連の作業が介護士の皆様には求められます。

服薬支援の際に介護職が気をつけること
お薬はご利用者様一人一人に合わせて作られています。そのため、必ず、ご利用者様のお名前と、カレンダーや一包化の袋に記載のお名前が同じであることをフルネームで確認しましょう。字が見づらい、日本語が読めない、等の介護士さんの場合は、一包化の袋に色分けをするなど、視覚的にわかるような工夫も可能です。施設には施設担当の薬剤師がいることが多いですので、一度相談してみましょう。
間違いなく配薬ができたら、その後は、一包化の袋からお薬を取り出す際に、袋にお薬が残っていないか、床などにお薬が落ちたりしていないか、ご利用者様が全て飲み込めているか、などの確認が必要です。
錠剤が大きくて飲み込めない、粉がむせて飲ませづらい等困りごとがあるときは、自己判断でお薬を砕いたり、粉を水に溶かしたりせず、まずは上長に相談し、その後薬剤師にご相談ください。たいていの場合、剤形の変更や服薬ゼリーなどにより、スムーズに服薬できるようになります。
外用薬の管理方法と注意点
塗り薬や座薬、目薬、シップ薬などの外用薬については、施設ごとに管理の方法が違うことが多いです。介護度の低い方は、居室で自己管理され、適宜自己判断で使用されていることが多いです。一方寝たきりなど介護度の高い方の場合は、事務所やナースステーションにて一括管理されており、必要時に介護士さんが持ち出して塗布されているところもあります。その際も注意点は同様です。必ずどなたに使用するのか、フルネームで確認した後、使用部位、使用回数の確認をしましょう。
水虫の薬など感染する疾患の薬剤塗布が必要なことも多いです。介護職の方にも移る危険性もありますので、感染を防止する観点からも手袋を必ず使用して服薬支援をされることをお勧めします。使用する手袋は、ご利用者様ごとに取り換えるのもお忘れなく!!
薬が床に!?貼り薬が剥がれた!?もし異変に気づいたら
毎日どれだけ注意していても、間違いが起きてしまうこともあります。その際に、お願いが一つあります。
『自己判断せず、速やかに報告を!!』
薬が床に落ちていた
例えば床にお薬が落ちているのを発見した場合、(この色のこの薬はたぶん〇〇さんの薬だろう・・・)と安易に服薬させてしまうと、後々違う方の薬だった・・・など大変なことになったりします。
お薬には「刻印」といって、薬剤に番号や名前が記載されていますし、服薬時点などもきっちり確認してから再度服薬の可否を検討する必要があります。
貼り薬が剥がれた
貼っているお薬がはがれてしまった場合も同じです。誰の薬がはがれているのか、再度貼るのか、新しいものを使うのか、など、全て確認が必要です。迷ったときは担当薬剤師に相談しましょう。
介護士も他職種との連携を

施設では、いろいろな職種の方が働かれています。看護師・ケアマネジャー・相談員・訪問診療の医師・薬剤師・栄養士などです。これはお願いですが・・・他の職種のかたと、是非仲良くなってください!!なんでも相談できる他職種の方を見つけておくことが、一人で悩まず、楽しく介護ができるポイントです。それぞれの分野で、正しい知識が合わされば、きっとご利用者様やご家族様にとって大満足な介護となることでしょう。
この記事を書いた人

真野有紀
JPEC認定薬剤師・実務実習指導薬剤師
大阪薬科大学卒業後、ドラッグストアにて一般市販薬販売に従事
その後神戸大学病院門前薬局での勤務や大阪赤十字病院門前薬局の管理者を経て、
現在は地域密着薬局にて管理者をしながら、在宅訪問や、施設在宅訪問に励んでいる
=あなたにオススメの記事はこちら=