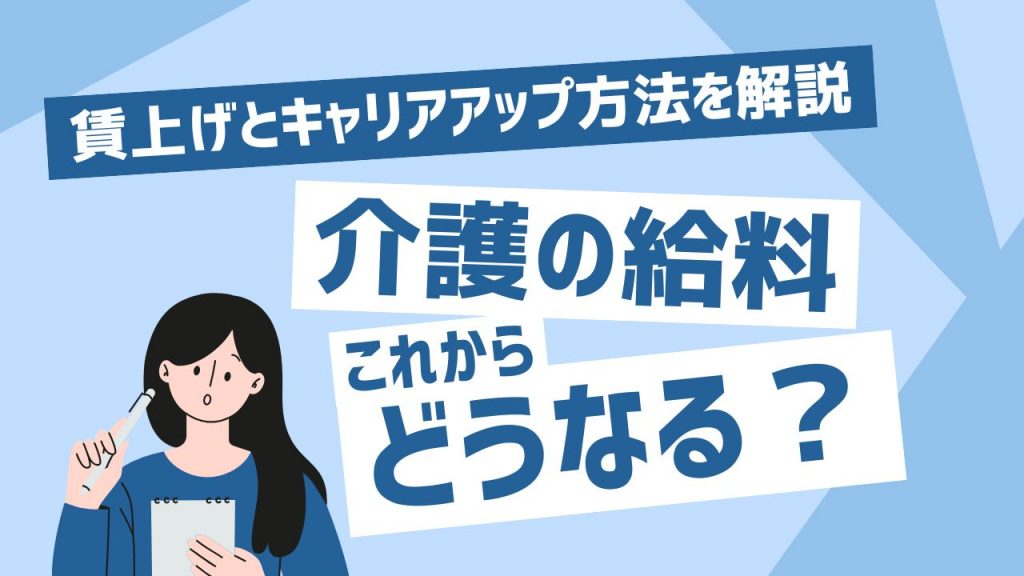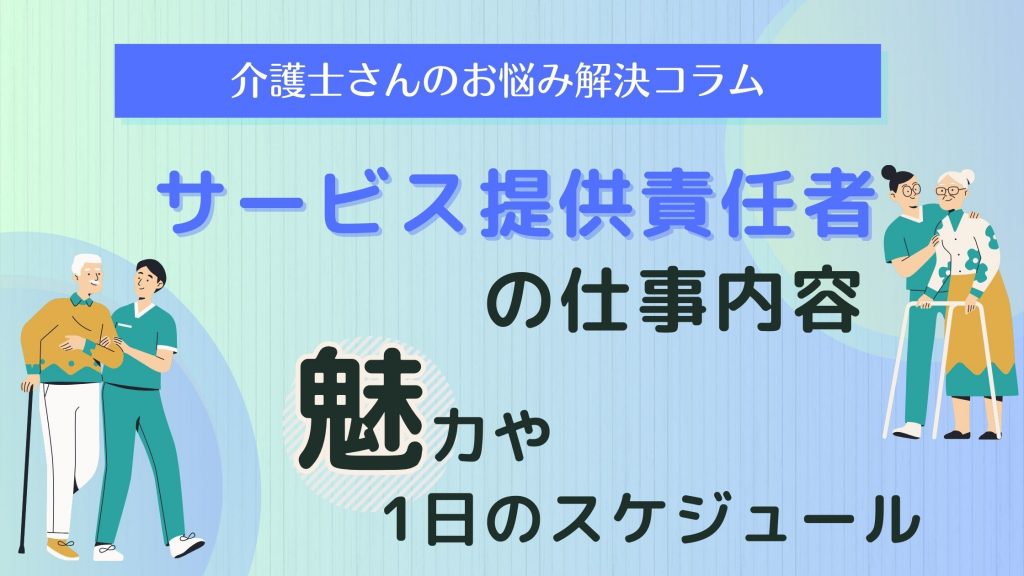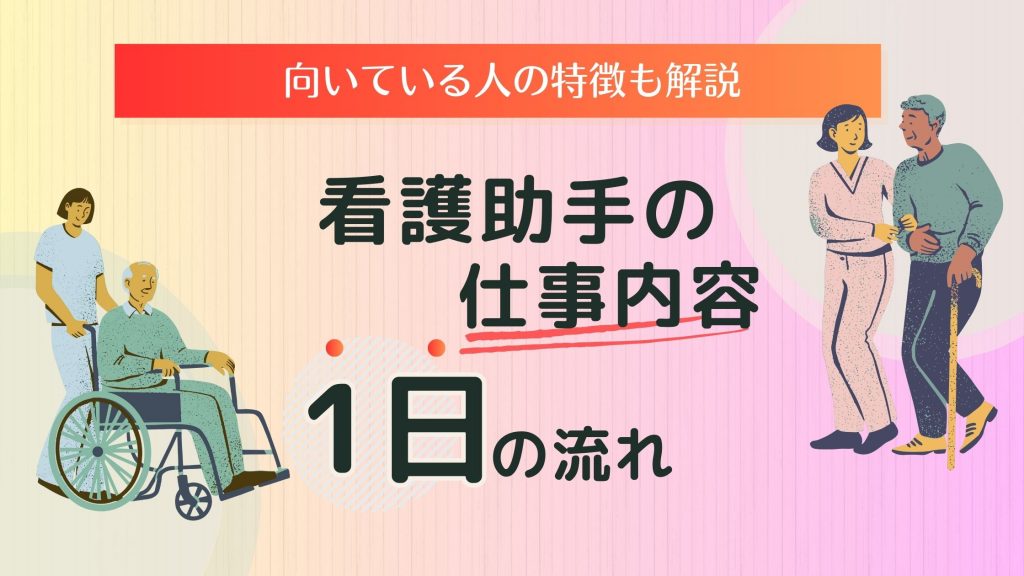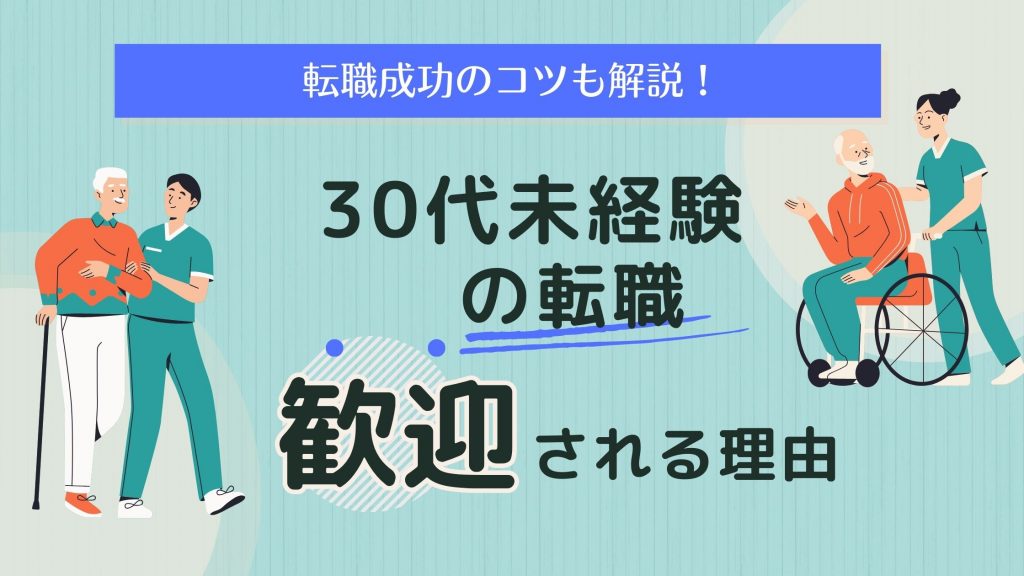こんな介護事業所は要注意!ホームページ・SNS・求人広告などから、その事業所の「本質」を見抜く方法
2022/02/14
最終更新日:2022/02/14
多くの方にとって、介護事業所や高齢者住宅(以下:事業所)は日常生活では縁のない場所です。利用するにせよ、働くにせよ「どういった場所かよく分からない」というのが正直な印象ではないでしょうか。

もちろん、どこの事業所もパンフレット、ホームページ、SNS、求人広告などの様々なツール(以下:自社メディア)を通じて、消費者や求職者に向けて積極的なアピールを行っています。しかし、それらは「よそ行き」の姿を紹介したものです。そこには記されていない事業所の「本質」を知っておかないと、利用してから、働き始めてから「こんなはずではなかった…」という事態になりかねません。
そこで、今回は、自社メディアから事業所の本質を見抜く方法を紹介します。
事業所の本質を見抜く方法4選
1 新着情報などの更新が殆どされていない

今は、どんな事業所でも自社メディアでの情報発信を行っています(していない「論外」な事業所もありますが)。しかし、単に「ホームページを作った」というレベルの事業所も少なからず見受けられます。
例えば「『新着情報』『ニュース』『トピックス』などの欄が1年以上更新されていない」などです。ここ2年近くは新型コロナウィルス感染症の影響で、事業所内での行事・イベントが思うように開催できなかったという事情はあるでしょうが、それでも会社として・事業所として、1年以上何も新たに発表することがないとは思えません。今は誰でも簡単に情報発信ができる時代です。それができていない事業所は「何かの問題を抱えている」と考えられます。

例えば、スタッフがブログやSNS更新を担当しているとしましょう。当初は週に1回などの頻度で更新されていたものが、徐々に頻度が減り、いつの間にか全く更新されなくなっている場合、どんな問題が考えられるでしょうか。
スタッフにブログやSNSを書かせるのは「業務命令」です。命じる側は「誰が、どの程度の頻度で書くのか」を明確にスタッフに指示し、そのための業務時間を確保できるようにしなくてはなりません。その業務命令が徹底されていないのは「指示が明確でなく、スタッフにしっかり伝わっていない」「スタッフが指示を理解できない、または遂行する能力がない」「スタッフに指示を守る意識がない」「長期間更新されていない事実を指示した側が把握できていない、または把握できても改善する意識がない」「更新を業務時間外(無償労働)でやらせようとしている」のいずれか(または、それらの複合)の理由が考えられます。職務遂行に関する組織としての意識・能力に問題があると言わざるを得ません。
2 「寄り添う」「おもてなし」など具体性の無い言葉を多用

私もそうですが、誰でも自分に都合が悪いことを発表するときは「イメージのいい言葉に言い換える」「わざと曖昧な表現を用いる」「話題を微妙にずらす」などの行動をしがちです。
自社メディアも同様です。「自分たちの事業所は質が良くない」と思っているところほど、「寄り添う介護」「温かい雰囲気」「おもてなしの心」「安心・安全」など、イメージはよいが曖昧な表現が多く使われます。
利用者目線で見た場合、事業所が安心・安全であるのは当たり前であり、知りたいのは「安心・安全のために、事業所が具体的にどのような取り組みを行っているか」です。例えば「非接触センサーでバイタルを常時確認」「スタッフの半数が介護福祉士」などです。しかしこうした具体的なアピール点がない事業所ほど、前述した様な表現を使いたがります。
求人広告も同様です。給与・休日日数・福利厚生・キャリアパスなどの具体的な内容で求職者に訴求できない事業所では「仲間との絆」「お客様の『ありがとう』が嬉しい」「誇りある仕事」などの表現が目立ちます。
3 スタッフ・利用者の顔写真が一切ない

「自社メディアに従業員・利用者の顔と名前が多く出ているか」も重要な判断材料です。(イベント時などの大勢が一度に写っている写真は除きます。1人で「先輩スタッフの声」「利用者の声」などとして登場している人がいるかどうか、です)
もし、自分の職場が素晴らしく「是非とも他の人に就労を勧めたい」「自分がここで働いていることを誇りに思う」のであれば、自らの名前と顔を出してもいいと思うスタッフも多いでしょう。もちろん「恥ずかしいので嫌だ」などの個人的な性格の差はありますが、何十人もいるスタッフの中で顔や名前を出せる人が1人もいないのは、あまり全うな職場環境でないことが想像できます。
利用者も同様です。私は2006年より介護業界で取材活動をしていますが、当初は利用者の顔を撮影することは絶対NGの事業所が殆どでした。しかし、今は自社メディアに利用者の顔を載せる事業所も増えています。そして、あくまでも私の個人的な肌感触ですが、そうした事業所は業界でも評判が良いところが多いと感じています。
かつて、事業所は「姥捨て山」に例えられ、そこを利用することは、本人にも家族にも「恥ずべきこと」という意識がありました。顔写真NGはその名残といえます。しかし、今は「介護サービスは、利用者が自分の意思で選ぶ」という前向きな思考が広まっています。サービス品質に自信がある事業所ほど、自信の表れとして利用者の顔出しを拒みません。利用者も、いいサービスを受け今の生活に満足しているからこそ顔写真を出したがります。
4 スペースに比して情報量が多すぎ

最後に提供する情報量です。もちろん自社メディアは「事業所の魅力を他人に伝える」のが目的ですから、ある程度の情報量は必要です。しかし、細かい文字でびっしりと書き込んでいるなど、スペースに比してあまりにも提供する情報量が多すぎると、受け取る側には「情報入手に時間がかかる」「余計な情報も入ってきてしまい、本当に必要な情報を見落としてしまう」などのデメリットが生じます。
必要以上に多弁な事業所は、自分たちの主義や想いを伝えることにばかり意識が向いていて、それを受け取る側の都合やニーズは二の次になってしまっている傾向があります。こうした事業所は介護サービスについても「利用者に合わせたもの」ではなく「自分たちの考えやルールに合わせたもの」を提供しがちです。もちろん、事業所の運営に際してはしっかりした哲学を持つことが重要ですが、それが利用者や従業員の自由や権利を損なうものであってはいけません。

この記事を書いた人

西岡一紀
フリーランスライター
新聞記者時代に海外旅行に目覚め、仕事の合間を縫ってヨーロッパ、東南アジアを中心に世界60ヵ国・地域に足を運ぶ。「目標は65歳までに100ヵ国」。ちなみに英語は全くだめ。船に酔いやすくクルーズも苦手。2019年秋脱サラしてフリーランスになり、現在に至る。
=西岡一紀さんの前回の記事はこちら=
=あなたにオススメの記事はこちら=