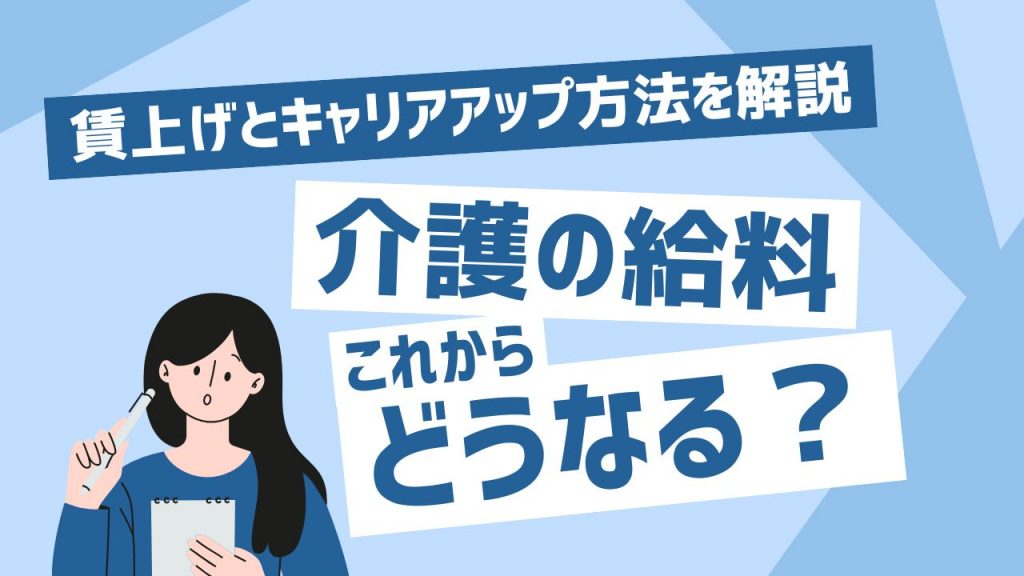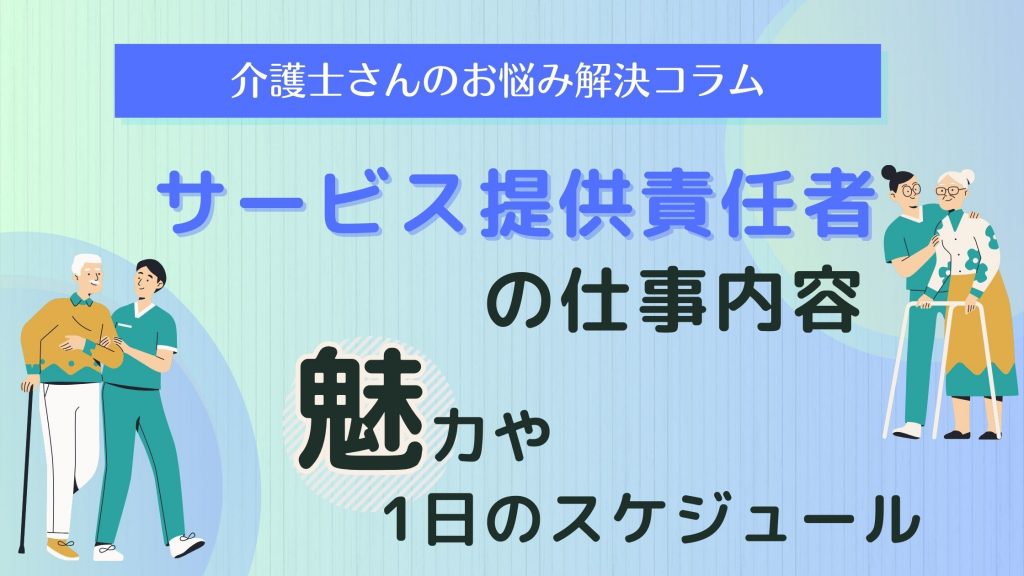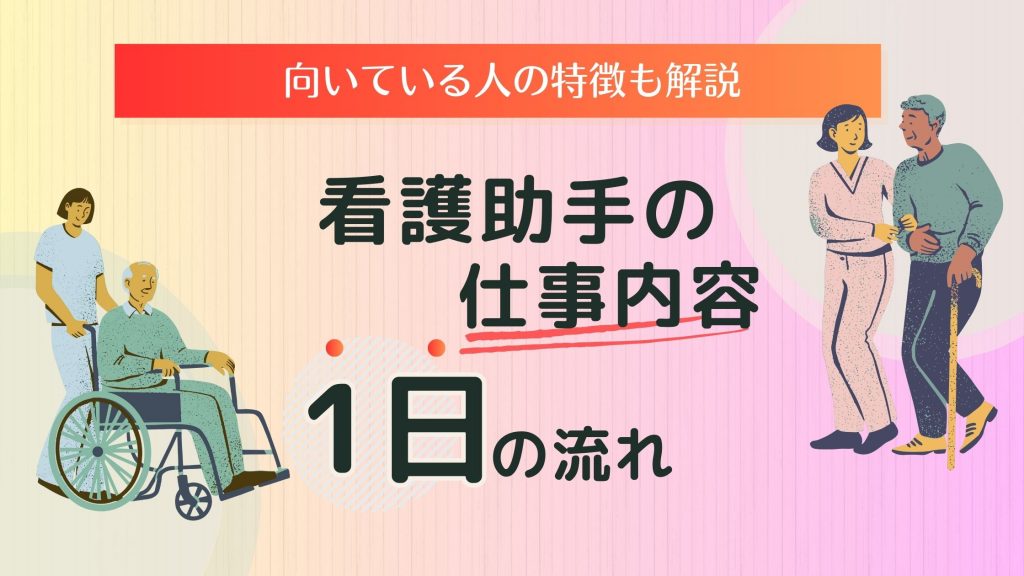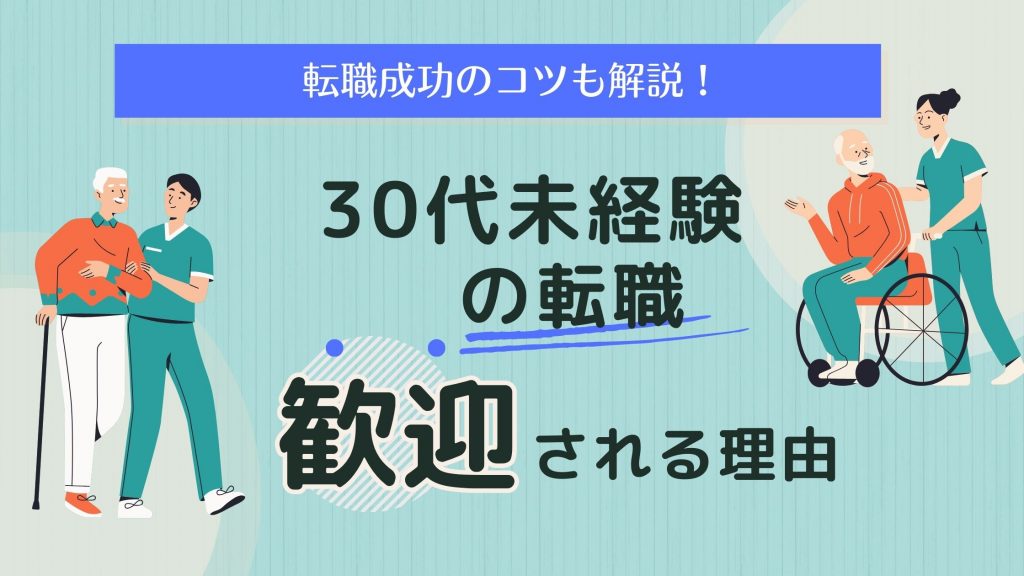備えあれば患いなし。コロナウイルス感染症対策、そして感染後の対応
2022/02/17
最終更新日:2022/02/17
世界的に猛威を振るう新型コロナウイルス感染症のオミクロン株。現在、身近な方が感染したり、また感染当事者になることも当たり前ぐらいの状況です。私自身も完璧に防ぐのは不可能だと考えていますし、以前私の家族もデルタ株に感染しました。その事実も踏まえて私なりの感染症予防、また感染後の対応について書くことで少しでも皆さんのお役に立てれば幸いです。

『感染予防』
感染経路として「家庭感染」が40%を超えています。職場と同様の感染対策が自宅でも出来ていますか?
介護施設では、免疫力が弱かったり、いろいろな疾患を抱える高齢者を介護しています。その為、どの施設でもマスク着用はもちろん出勤時はアルコールで手指消毒し、検温、SPO2計測、体温測定をしてから介護業務を開始すると思います。では、自宅でも職場と同じくらいの感染予防が出来ていますか?
高齢者施設の入居者様の感染はやはり職員の可能性が高いです。ご勤務される皆様は新型コロナウイルスが流行してから、自発的に日常生活の活動を制限されている方がたくさんいると思います。私もそうです。人が多く集まる場所、観光地、遊園地などは数年行ってません。それでもここまで感染が広がってくると、いつ、どこで感染するかわかりません。ですので、「もし自分が感染者だったら」「家族が感染者だったら」を考えて行動しなくてはなりません。少しでも感染確率を下げるために「飛沫感染」「接触感染」の予防が大切です。参考例として私の場合をお話します。

帰宅後は直ぐに脱衣場に行って不織布のマスクをゴミ箱に捨て、手洗い、うがい、洗顔、洗眼、そして外で着ていた服を脱ぎ、脱いだ衣類は洗濯機で直ぐに洗い部屋着に替えます。この時に風呂が沸いているなら入浴します。なるべく洗身してから家族と会います。沸いていないなら入浴準備をします。その後、マスクをして家族と会います。食事中はなるべく黙食となるようにしています。料理を取るときも菜箸を使います。食事が終わったあとにマスクを装着し会話をします。寝るときもマスクをして寝ます。あくまでも私の場合ですので、参考程度にお考えください。
手指消毒はアルコール度濃度70以上が効果的。適切な手指消毒をしましょう。
アルコール(エタノール)は濃度が濃いほど殺菌効果が高いと言われています。デメリットとしては肌荒れの心配が高くなります。もちろんそれ以下のアルコールでも一定以上の殺菌効果はあります。一番大切なのは適正な手指消毒をすることです。詳しくは「厚生労働省(正しい手指消毒)https://www.mhlw.go.jp/content/000501122.pdf」をご覧ください。
抗原検査キットは感染初期のオミクロン株を拾いにくい?

抗原検査にはインターネットなどで容易に買える「研究用」と厚生労働省が承認した「体外診断用医薬品」があります。体外診断用医薬品の抗原検査キットは国の治験を経て承認されたもので医療機関や自治体が使用しているものと同じです。購入時に使用者氏名記入や薬剤師から使用方法の説明を受けます。一方で研究用は国の承認を得ていないので性能は不明です。実際に両方使ってますが、感染初期はどちらも陰性の場合が多いです。この前友人から聞いた話ですが、「体外診断用医薬品」の抗原検査で陰性が出た日にPCR検査もおこなったら、抗原検査では陰性。PCRで陽性の結果があったと聞きました。インフルエンザも同じですが、ある程度ウイルスが増殖しないと抗原検査キットでは拾いにくいのかもしれません。
なるべく定期的にPCR検査を受けるべき
抗原検査は上記のような可能性があるのでなるべくPCR検査を定期的に受けたほうが早期発見に繋がると考えます。私の職場では現在、PCR検査を週2回行っています。また抗原検査キットも多数用意しております。職員、利用者様の体調変化時には迅速な対応を心掛けております。
熱が出てからでは遅いかも?少しでも風邪のような症状があれば疑うべき
オミクロン株感染について、私の知人のほとんどは始めに喉の痛みや咳の症状があり、その後に熱が出る(出ない方も多数いました)ケースが多いです。この時期は花粉症や乾燥により喉を傷めるケースもあるので、判断が難しいこともありますが、風邪の症状がある場合は軽い症状であっても、直ぐに病院受診をすることが良いと思います。熱が出てからでは、すでに発症して感染を広げている可能性も十分考えられるからです。早期発見早期受診をおすすめします。
検温、SPO2はこまめに。出来れば、朝・昼・夕

早期発見をするためにも検温、SPO2は細目に行うことが良いかもしれません。業務開始前、昼休み、業務終了後に行い「ウイルスを持ち込まない、持ち帰らない」ことが大切です。
要介護高齢者の状態変化を注意深く観察。朝は大丈夫でも、午後から症状が現れるケースも
加齢に伴う心身の変化により病識が薄くなったり、病気を感じにくくなることが高齢者の特徴です。特に独居高齢者の場合は家族等がいないので体調の変化に気付きにくいことが考えられます。その為、デイサービス等で迎えに行ったときやまた利用開始した朝では熱もなく、体調変化が見られなくても、昼や夕方に発熱した経験をされている介護者は多いと思います。今回はそれがコロナウイルス感染の場合もあるので、体調変化には細心の注意を払うべきと考えます。少しでも体調が悪くなったら受診をして抗原検査やPCR検査を受けたほうが良いでしょう。
経験談から、ワクチンの効果は大きい
ワクチンについては副反応などもあり、アレルギー反応がおこる方には重篤な作用が起きてしまう可能性もあります。ですので強制的に接種を勧めることはありません。ですが、ワクチンを接種していない友人の話とワクチンを接種している友人の話をまとめると、ワクチンの効果はやはり大きいと思います。
手洗い手指消毒以外に、うがいや目を洗う(洗眼)ことも重要
現在職場ではマスクの他に使い捨て手袋着用、そして目の保護のためにフェイスガードかゴーグルか保護メガネの着用も行っています。手洗い以外にうがい、そして洗眼も感染予防に繋がると考えております。

飛沫感染の防止の為、マスクを外してしまう利用者様にも根気よくマスク装着をして頂くことが大切
認知症等によりマスクをすぐ外してしまう利用者様もいらっしゃると思います。ですが、その利用者様を飛沫感染から守るためにもマスク装着を根気よくお願いしましょう。
衣類の着脱時は飛沫感染の危険性が。浴槽からあがったらマスク着用を
入浴前や特に入浴後には身体が濡れていたり、水蒸気の関係で脱衣所ではマスクはとても息苦しく、衣類着脱時にはマスク未装着のことが多いです。その為飛沫感染リスクが高まります。浴槽からあがったら、なるべく早くマスクを装着したほうが良いと考えます。
使い捨て手袋は入居者毎に替える

利用者様の処置をしたり身体等に触れた場合は使い捨て手袋を替えたほうがよいと考えます。特に入浴時は身体に直接触れます。接触感染を防ぐためにも使い捨て手袋を替えて次の利用者様を介助しましょう。
『コロナウイルス感染後の対応』
職員が陽性になった場合

例えばデイサービスであれば対象者はデイサービスの職員、利用者様全員と考える、ユニットであればユニット全体が陽性になったと考えることから始まります。この時点でできれば全員に抗原検査又はPCR検査をすることが良いでしょう。そしてユニット閉鎖やデイサービス閉鎖などをして職員の行き来を遮断し、同時に消毒も行います。その中で状況を時系列に整理して、誰が一番接したかなどを保健所に相談して濃厚接触者を限定していくことです。現在、感染者が多くいるので保健所とは連絡が取れない場合も想定できます。時間が経てば経つほど感染拡大する可能性があるので先ずは陰性の確認が取れ、濃厚接触者ではないことが解るまでは自宅待機にすべきです。すべては保健所の判断で動きます。
利用者様、入居者様が陽性になった場合
こちらも同様に、デイサービスであれば対象者はデイサービスの職員、利用者様全員と考える、ユニットであればユニット全体が陽性になったと考えることから始まります。この時点でできれば全員に抗原検査又はPCR検査をすることが良いでしょう。そしてユニット閉鎖やデイサービス閉鎖などをして職員の行き来を遮断し、消毒も行います。状況を時系列に整理して、誰が一番接したかなどを保健所に相談して濃厚接触者を限定していきます。現在、感染者が多くいるので保健所とは連絡が取れない場合も想定できます。時間が経てば経つほど感染拡大する可能性があるので先ずは陰性の確認が取れ、濃厚接触者ではないことが解るまでは自宅待機にすべきです。
入居者様の場合は陽性の可能性がある場合や陽性が判明した時点でゾーニングを開始します。レッドゾーン(感染者居室)、イエローゾーン(感染者居室の直ぐ外に防護服の着脱場所)、そしてグリーンゾーン(感染者以外)を区分けし行き来を遮断します。陽性者(感染者)がユニットリビングにいることが多かった場合はユニット全体をレッドゾーンと考えるべきでしょう。そしてユニット入口をイエローゾーン、廊下をグリーンゾーンとします。
ゾーニングはとても重要、しっかり区別し必ず守ること
ゾーニングは感染拡大を防止する大事な区分けです。必ず守りましょう。
感染者の介護は防護服をしっかり装着すること

防護服は自分を守り、また他者を守ることに繋がります。施設により防護服の定義は違うと思いますが、キャップ、フェイスガード、N95マスク、ガウン、二重使い捨て手袋、シューズカバーを装着し、食事などの容器はすべて使い捨てに変更。専用のフタが付いているペダル式ゴミ箱などを使用しましょう。(事前に使い捨ての食器やゴミ箱などを用意しておく必要があります。)
なるべく担当者は固定すべき
入居者様の対応は交代勤務ですが、その日の担当をなるべく変えず固定すべきでしょう。例えばAさんが感染者対応を午前中してBさんは一般者の対応をして、午後はAさん、Bさんが交代などは基本的にはしないほうが良いです。その日はAさんが対応すべきです。
指示は全て保健所から受けます。自分勝手や事業所勝手は基本NGです

新型コロナウイルスは2類感染症になります。保健所に随時報告や確認を行い指示を仰ぎましょう。
この記事を書いた人

加藤 英明
介護福祉士・主任介護支援専門員
社会福祉法人熊谷福祉の里にて、特別養護老人ホームクイーンズビラ桶川副施設長として従事する。介護講師や地域福祉団体『埼玉県央ケア協会』の共同代表として、県央地域を中心に地域福祉向上のため活動中
=加藤英明さんの前回の記事はこちら=
=あなたにオススメの記事はこちら=