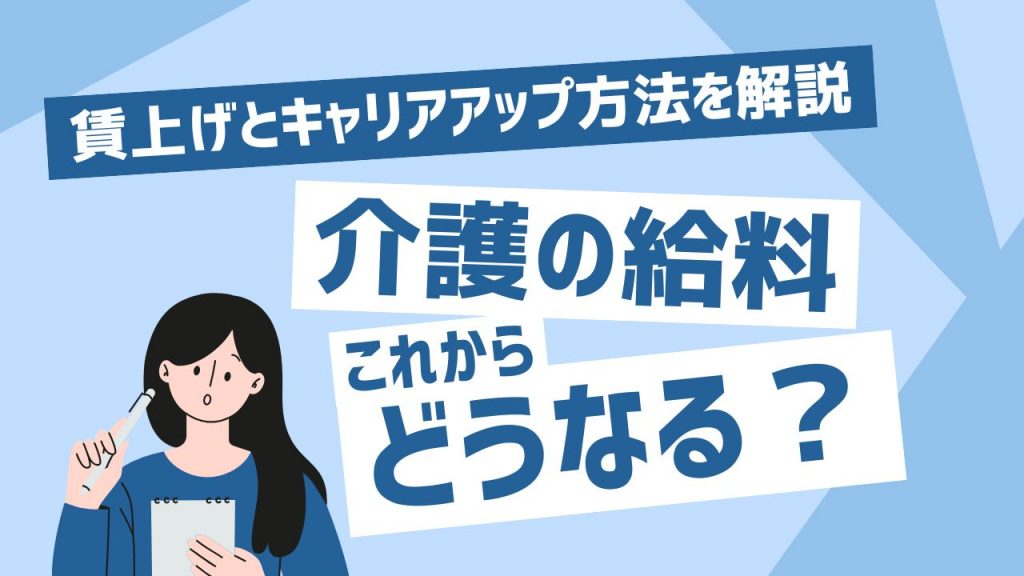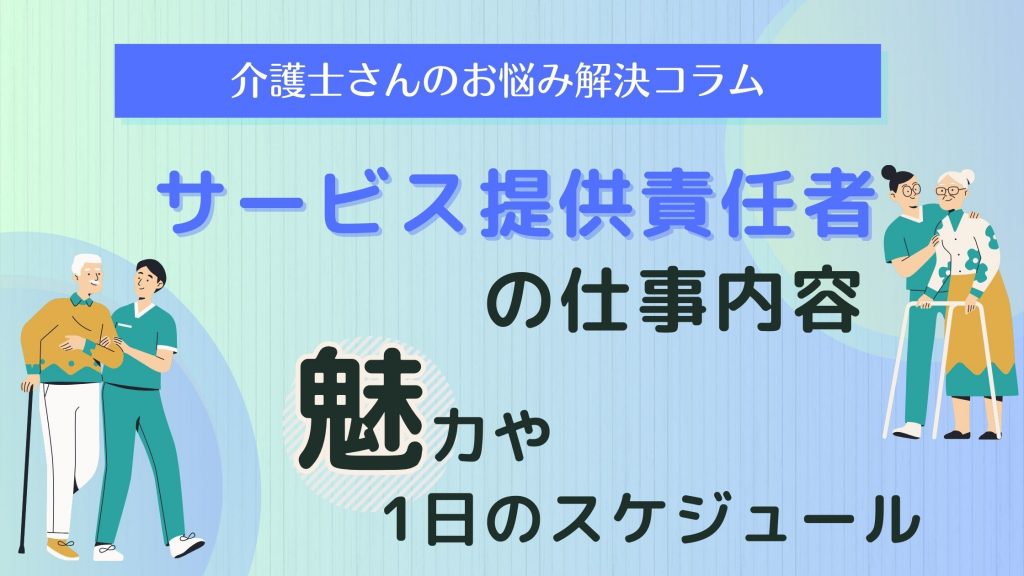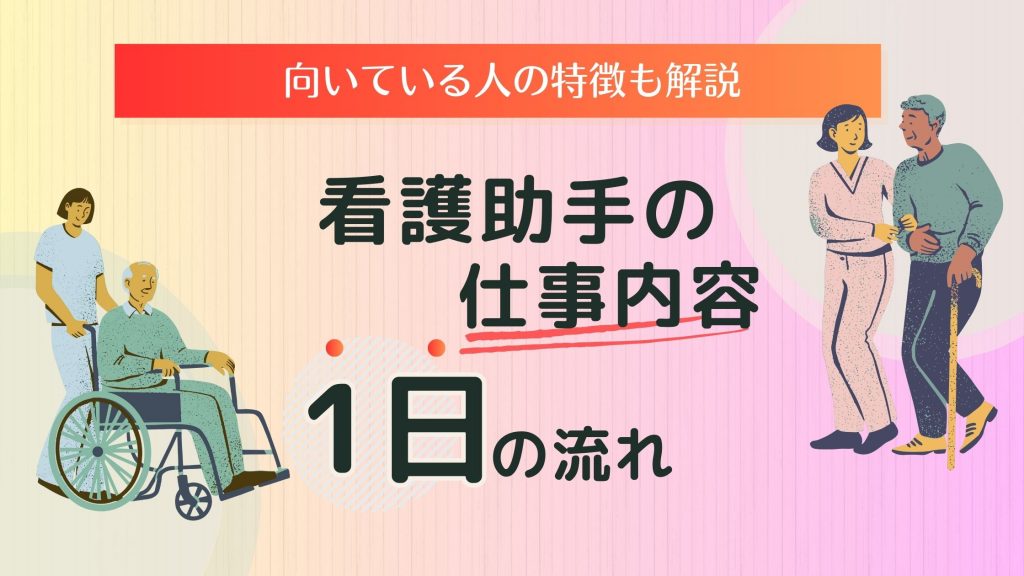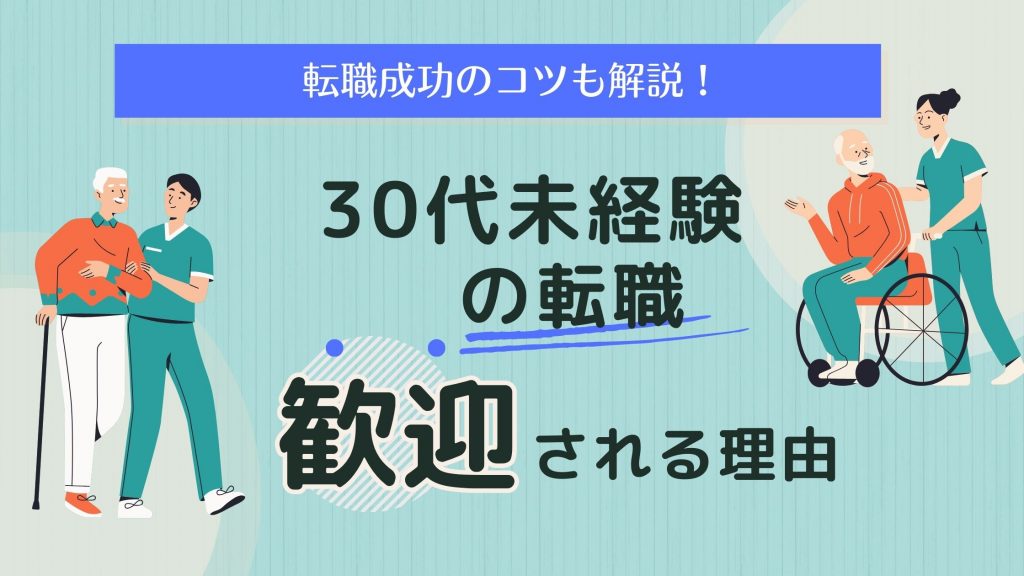介護職1年目の方へ、介護施設に入職した時のアドバイス
2022/04/21
最終更新日:2022/04/21
桜咲く4月。新しい生活の始まりを迎えた方もたくさんいらっしゃると思います。希望を胸に、頑張っている皆様に幸あれ。

ですが、人生は常に順風満帆とはいきません。澄んだ青空の時もあれば、暗雲が広がり雷や大波の時もやはりあります。嫌なこと、辛いことを乗り越えた時に人は成長します。
先輩や上司から注意された!!怒られた!!そんな時は、「自分の成長のチャンスだ!!」と辛くても思うようにすることが自分のためになります。頑張ってください。それでは、介護の世界で頑張る方にアドバイスさせて頂きます。
元気よく笑顔で挨拶をしましょう

この記事が掲載される頃には皆様は既に、何日か介護現場で就労されていると思います。介護現場の印象どうですか?(いいにくいこともあるかもしれません(笑))
職場には友人や仲間が出来ましたか?仲良くなったおじいちゃん、おばあちゃんは出来ましたか?先輩、上司に慣れるには少し時間かかりますが、それはお互い様なのです。双方にしっかり歩み寄りたい気持ちがあれば、必ず上手くいきます。
関わり方や、介護の仕方も利用者によって様々

高齢者施設には身体的介護が必要な方もいますが、認知症高齢者も多く、関わり方など覚えることがたくさんあります。
これから皆様は介護現場において様々な勉強をされることだと思います。要介護高齢者の接し方、ボディメカニクス等、もちろん初めての方もいれば学校で習った方もいます。
習った方からすれば「そんなの聞いたよ」と思うかもしれません。医療も介護も日進月歩で日々進化します。介護技術や接し方も同じです。復習だと思って何度も習ったり実践してください。
また介護ロボットやIOTなどもこれから、たくさん導入されていきます。それでは認知症サポーター養成講座で教える認知症の方への接し方の心得を書かせて頂きます。職場でも活かせることはきっとあります。是非、参考にしてください。
認知症の人への対応心得“3つの「ない」
1驚かせない
2急がせない
3自尊心を傷つけない
具体的な対応の7つのポイント

- まずは見守る
認知症と思われる人に気づいたら、本人やほかの人に気づかれないように、一定の距離を保ちさりげなく様子を見守ります。近づきすぎたり、ジロジロ見たりするのは禁物です。
- 余裕を持って対応する
こちらが困惑や焦りを感じていると相手にも伝わって動揺させてしまいます。自然な笑顔で応じましょう。
- 声をかけるときは1人で
複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすいので、できるだけ1人で声をかけます。
- 後ろから声をかけない
一定の距離で相手の視野に入ったところで声をかけます。唐突な声かけは禁物。「何かお困りですか」「お手伝いしましょうか」「どうなさいました?」「ごゆっくりどうぞ」など。
- 相手に目線を合わせてやさしい口調で
小柄な方の場合は、体を低くして目線を同じ高さにして対応します。
- おだやかに、はっきりとした滑舌で
ご利用者様は耳が聞こえにくい方が多いので、ゆっくりとはっきりとした滑舌を心がけます。早口、大声、かん高い声で捲くしたてないこと。またご利用者様個々の土地の方言や風習を調べてコミュニケーションを取ることも大切です。
- 相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する
認知症のご利用者様は急かされるのが苦手です。同時に複数の問いに答えることも苦手です。相手の反応を伺いながら会話をしましょう。 たどたどしい言葉でも、相手の言葉をゆっくり聞き、相手の言葉を使って推測・確認していきます。
そして一番は元気よく笑顔で挨拶しましょう!!これは、ご利用者様だけではなく、職場の仲間にも同様です。これは周りの人だけではなく、自分にもプラス効果があるのです。
元気よく挨拶、笑顔になることで、脳が活性化し、ストレス緩和、免疫力アップ、α波やβ波が出て「やる気満々」、便秘解消、顔の筋肉が引き締まり小顔効果など効果絶大!!先ずは作り笑顔で良いのでやりましょう。やらなきゃ損です。直ぐに実行しましょう。これで、今日一日は良い日になります!!
新入職員の皆様、忘れないでくださいね。認知症の一番の特効薬は「薬」ではありません。「笑顔」です。 『笑いは神様が下さった万能薬』なのです。
心と身体の管理大切です
仕事は何でもそうですが、お金を稼ぐことは簡単な事ではありません。私も仕事している時、正直しんどいと思うことはあります。誰もが一緒だと思います。立場は違えど人それぞれ悩みはあるものです。
ストレスは適度な量なら身体に良いと言われています。私達の仕事は直接要介護者の身体に触れて援助する対人援助職です。ストレスを受けやすい仕事でもあります。ですが、仕事は仕事。職場を出たらなるべく仕事の事を忘れてストレスを軽減し、趣味の時間を過ごし、十分に休息を取りましょう!!
失敗は誰でもするもの

上司や先輩の指示に従い、担当する利用者様の笑顔がいつも見れたらうれしいですが、時には失敗することもあります。そのような時は、現状をしっかり受け止め、記録、報告、改善し、その失敗を生かしましょう。
介護業務ではヒヤリハット、事故報告があります。ご利用者様が急に立ち上がったり、歩き出そうとしたり、いろんなことが起こります。仮にマンツーマンで対応したとしても急な動作に瞬時に対応するのは困難な時もあります。だから、ヒヤリハットや事故はゼロにはできないと考えます。車椅子やベッドからずりの落ち。室内歩行時に急な意識消失もあるかもしれません。でも、個別の記録をしっかり付け、その方の行動や病状把握をより細かく想定出来たなら、限りなく減らせることは出来ると思います。
有名な方の言葉を少し紹介致します。
◎真に称賛すべき人間の特質とは、困難な時の粘り強さである
音楽家 ベートーヴェン
「介護をする上で困難なことはいっぱいあります。でも諦めず進み続けることが 自分自身の強み(ストレングス)にもなるし周りからも認めてもらうことになります」
◎困難な仕事を避けてはいけない。困難な仕事に立ち向かい克服してこそ、真の経営者といえる 松下電器創業者 松下幸之助
「皆さんも毎日いろいろな介護の仕事を通じて日々成長されていかれると思います。その中で人をまとめる役(リーダー)や上司から、いろいろな研修に参加してほしいと言われることがあります。日々の介護業務で忙しいかもしれません。でも、そのようなときは、自分に「成長するチャンスだ!!」と言い聞かせて、是非チャレンジしてみてください。楽して得た知識や経験はあまり活かされることはありませんが、苦労して得た知識や経験こそ、これからの自分自身に必ず活かされます。
◎人間がいろんな問題にぶつかって、「はたと困る」ということは、すばらしいチャンスなのである。 ホンダ創業者 本田宗一郎
「仕事でも普段の生活でもいろいろな問題にぶつかることはよくあります。そのような時は当然「う~ん・・困ったなあ」となります。でもそれがチャンスかもしれません。例えばトイレで日々排泄介助をしているとき、立位で清拭するご利用者様がいたとします。そのような場合は、手すりに掴まり頂き、ご利用者様を支えながら清拭します。
仮に清拭がたくさん置いてある場所の位置が遠ければ手が届かない。そのような時は、「手の届くところに清拭を準備できる場所があればいいのに?」と思います。上司に相談すると、「清拭を用意して手に届く範囲に置いてから行うように。」と言われるかもしれません。でも、初めから清拭をまとめて置く場所が手の届く範囲にあったら業務効率化になるかもしれません。ここで問題なのは、そのことに気付くことの大切さだと思います。
人間誰もがその環境に慣れてしまうと、その環境の中で物事を完結しようとしてしまいます。ただ、それが悪い事だとはいいません。でも、もしかしたら、少しの工夫でやりやすくなることもあると思います。その工夫こそが環境の「改善」であり、気付いた人間の「成長」に繋がり、それをカンファレンスなどでスタッフ皆様に提案することで、スタッフ皆様も気付きのチャンスを得ることになります。業務改善になれば、ご利用者様も職員もプラスになるのです。
パーソナルスペースや個別ケアについて

想像してください。ガラガラの電車に乗った時、自分が座ったすぐ横に後から来た人が座ってきたら、どう思いますか?(気持ちいいですか?なんか嫌だなぁ?周りがガラガラなのになんで横に座るの?等)普通なら気分良くないと思います。
人には皆、パーソナルスペースがあります。パーソナルスペースとは、他人に近付かれると不快に感じる空間のことで、パーソナルエリア、対人距離とも呼ばれます。一般に女性よりも男性の方がこの空間は広いとされていますが、社会文化や民族、個人の性格やその相手によっても差があると言われています。またその時の状況・心理状態によっても空間の大きさは変化します。
初めてお会いするご利用者様、その方にもパーソナルスペースがあります。適切な距離感を考えることも覚えておきましょう。
また、既にご利用をされているご利用者様でも機嫌が悪かったりすればパーソナルスペースは広がっています。家族や職場の仲間も同様です。その日その時にこちらの都合と関係なくパーソナルスペースの大きさは変化します。
個別ケアについて
同じ病名や同じ身体状況でも、ケアの方法は全く一緒ではありません。私達もそうではないでしょうか?親や家族、子供、又は双子で外見が似ていても必ず違うところはあります。
「一人一人をしっかり観察してその方に添った介護をする」ということです。例えば、入浴時、身体を洗うとき、どこから洗いますか?(頭、胸、足?)皆一緒でしょうか?違いますよね。人それぞれ洗い方も違います。入浴方法も個性があるようにすべてに個性があります。それをしっかり把握することから個別ケアが始まります。
いろいろな資格にチャレンジすることもアリ!!
4月から職場でご活躍されている皆様。これからいろんな経験や知識、技術を学んでいきます。仕事はなんでもそうですが、学んでいる時は辛いこともあるけど、同時に遣り甲斐もあります。
慣れてきて、経験を積んだら、介護には様々な資格があります。是非チャレンジしてみてください!!

介護とは人類学を学ぶようなもの。
自分自身をアセスメントしてモニタリングまでの一連作業を繰り返すことで更なる成長へ
私達の仕事は「人」が相手になります。商品を製造、陳列、販売したりするのとは大きく異なります。人にはそれぞれ性別、個性、歴史、言語、社会的慣習など、様々な要因が組み合わさり「個性」を形成します。
介護とはその「個性」を理解し、その方の「らしさ」を体現し生活の質「QOLの向上をすることです。だから学びも多く自分自身も学ばせていただける尊い仕事だと思います。入居者様とはいろいろ話をして、その人の「らしさ」は何なのか?見つけましょう!!
緊急時、災害時、感染症発生時などは焦らず対応
目の前で利用者様が倒れてしまう。「いつもと様子が違う。意識がない」 ⇒ 「救急車を呼ぼう!!」となることもあります。そんなときはまず「慌てない」ことが一番です。
自分では判断できないときは、周りに助けを求めましょう。介護とは一人で行うことではありません。たくさんの方と連携して行うものです。常に相手を思いやる真心を持ち続けるようにしましょう。