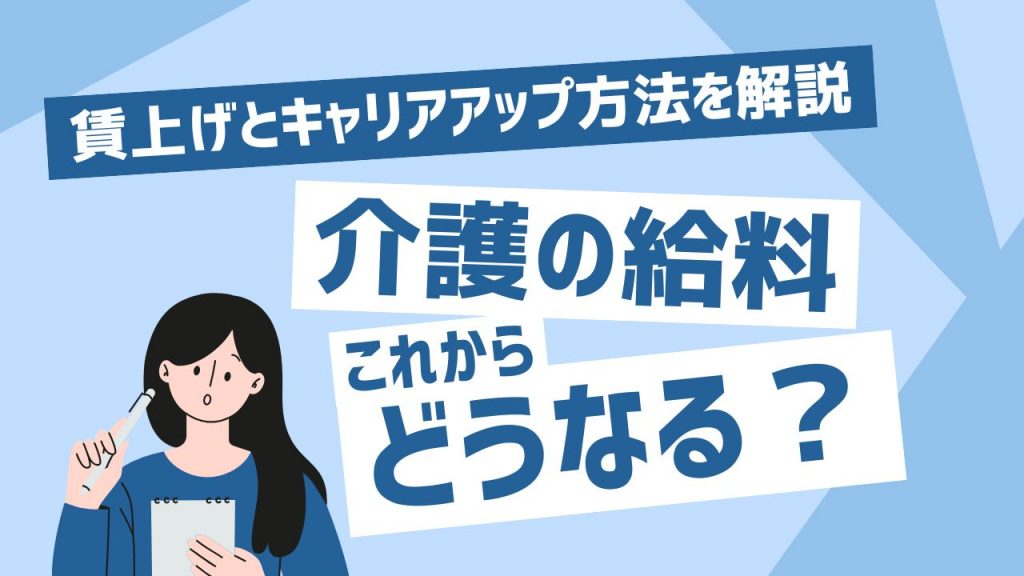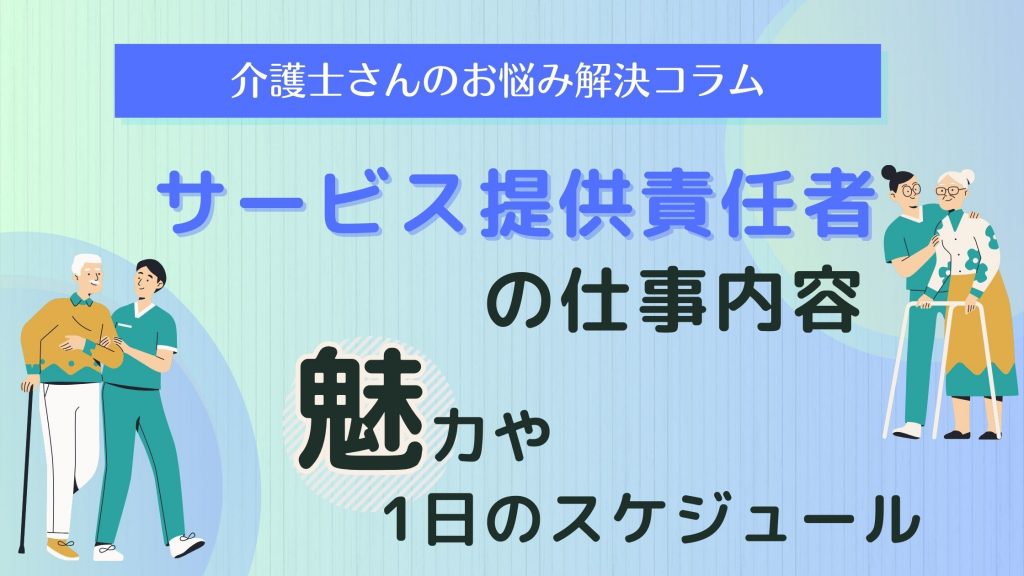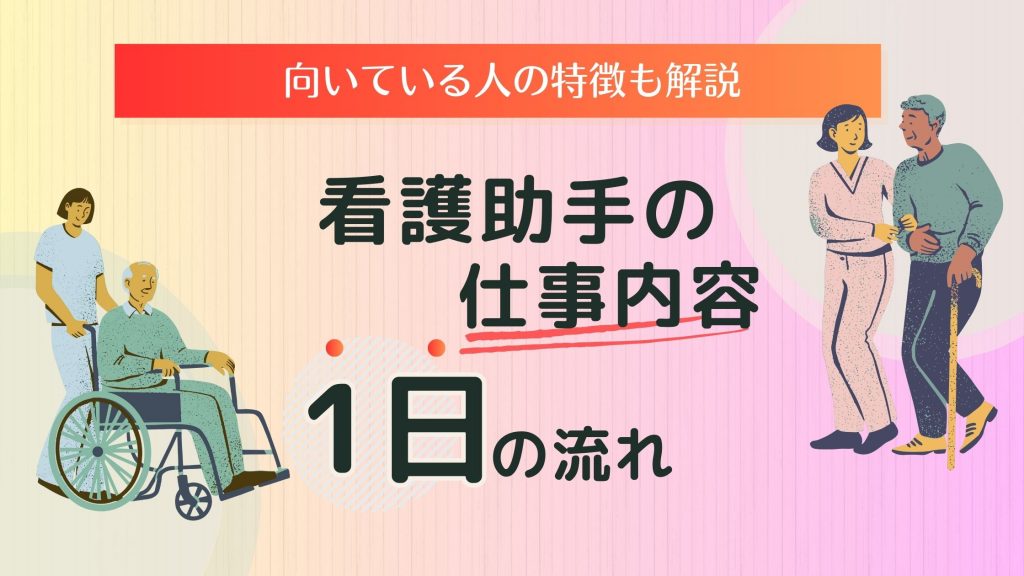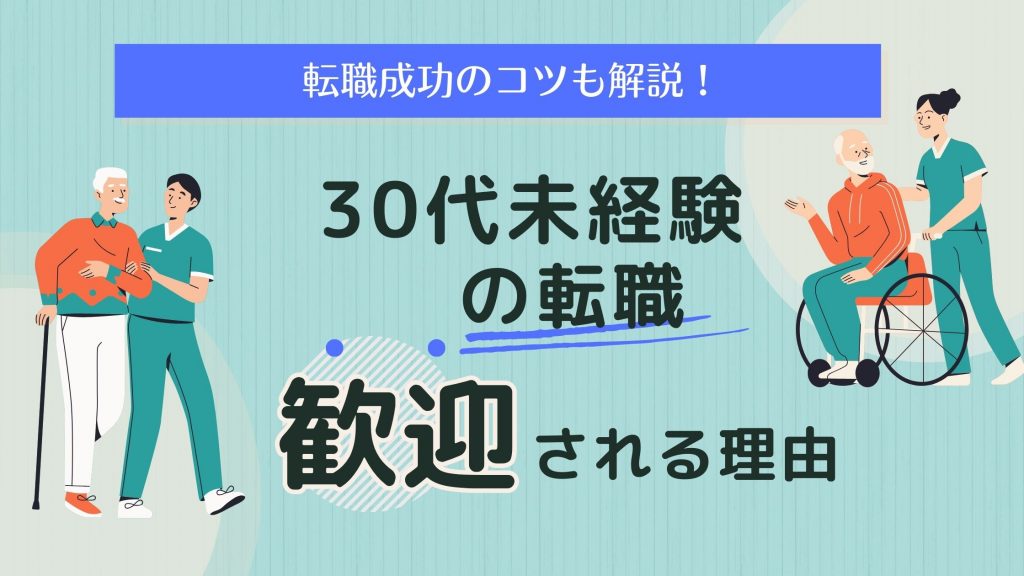夜勤16時間は違法?労働基準法や介護現場の実態、休憩時間について徹底解説
2025/02/01
最終更新日:2025/02/01

夜勤16時間勤務をこなす中で「これって違法じゃないの?」「休憩時間が取れないのは仕方ないの?」と、疑問を感じていませんか。
介護の夜勤は、労働基準法の条件を満たせば法律違反ではありません。しかし、一人で夜勤をこなすワンオペ夜勤や休憩時間が取れないことなど、大きな課題があります。
本記事では、労働基準法や介護現場の実態、休憩時間の取り扱いについて詳しく解説し、適切な働き方を見つけるためのポイントをお伝えします。
本記事を参考に、介護の夜勤を安心して働くヒントとしてください。
夜勤の16時間勤務は労働基準法違反ではない
16時間勤務は一見法律違反のように思えますが、条件を満たせば違反にはなりません。
ここでは、16時間勤務が違反にならない理由や休憩時間、違法性が問われるケースについて考察します。
労働基準法から読み解く16時間勤務
16時間勤務は、労働基準法の定める1日8時間・週40時間を超えるため、原則的には過剰な労働時間と捉えられます。
しかし、1か月単位で変形性労働時間制を採用すれば、夜勤の16時間は違法になりません。
変形性労働時間制は一定の要件・期間について、1週間の労働時間が40時間を超えない限り、1日8時間を超えてもよいとする制度です。
ただし変形性労働時間制を採用しても、長時間労働を無制限に設定できるわけではなく、労働時間の上限・時間外労働や休日に関する規定は守らなければなりません。
出典:e-GOV 法令検索「労働基準法 第三十二条の二 」
休憩時間は必要ない?
労働基準法では、勤務時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩時間を労働者に与えることが義務付けられています。
そのため、16時間勤務で休憩時間が適切に設定されていない場合、違法となります。
休憩時間は労働者が自由に利用できる状態でなければならず、職場内で拘束される休憩は認められません。
たとえば、休憩時間中に作業するように指示を受けたり、緊急対応を求められたりする場合は、法律違反となる可能性があります。
そのため、しっかり休憩できるかどうかは、働きやすい施設かどうかを見極めるポイントになるでしょう。
16時間夜勤と8時間夜勤の違い
16時間夜勤と8時間夜勤の違いは、勤務時間の長さだけでなく、ライフスタイルや健康への影響においても大きく異なります。
本章では、16時間と8時間の夜勤の違いを比べてみます。
16時間夜勤
16時間夜勤は2日分の労働を1回で行うため、勤務日数が少なくなり、通勤回数も半分ですみます。
また、夜勤明けの日は多くの時間を使え翌日も休みのため、休日が増えたようなお得な気分になるものです。
しかし、まとまった休みを取りやすくなる一方で、長時間労働による体力的・精神的な負担が増えることが課題でしょう。
8時間夜勤
8時間夜勤は勤務時間が短いため、心身への負担は軽減されるでしょう。
ただし、夜勤が連続する可能性や、夜勤の翌日に日勤業務となるケースもあるため、生活リズムへの適応が求められます。
また、深夜の出勤・退勤となる場合もあるため、不安に感じる方も少なくありません。
さらに、休日の翌日が夜勤にあたっている場合、休日の深夜には職場へ向かわないといけません。施設によっては、夜勤明けが休みのところもあります。
8時間夜勤は16時間夜勤と比べて心身の負担は少ないですが、休日が少なく感じる点がデメリットといえます。
16時間夜勤のスケジュールと業務内容
介護現場の16時間夜勤は食事介助や排泄介助だけでなく、就寝介助や起床介助、安否確認なども行います。
16時間夜勤の一般的なスケジュールは、以下の表を参考にしてください。
| 時間 | 仕事内容 |
|---|---|
| 16:00〜 |
【出勤・申し送り】 ● 日勤者から利用者の様子や注意点を共有し引き継ぎを行う |
| 17:00〜 |
【夕食】 ● 夕食の準備や配膳を行う ● 必要に応じて食事介助も提供する |
| 18:30〜 |
【夕食片付け】 ● 食後の片付けや口腔ケアを行う |
| 20:00〜 |
【就寝準備】 ● 就寝するために以下のケアを行う ・トイレ介助 ・排泄介助 ・着替え介助 ・ベッドへの移乗 |
| 21:00〜 |
【就寝介助・巡視】 ● 睡眠薬の服薬介助 ● 1〜2時間ごとに巡視を行い安否確認を実施 |
| 22:00〜 |
【記録】 ● 介護記録を記入 |
| 0:00〜 |
【巡視・体位交換・排泄介助】 ● 体位交換が必要な方のケアを行う |
| 2:00〜 |
【休憩】 ● 2時間ごとに交代で休憩・仮眠を取る |
| 4:00〜 |
【巡視・体位交換・排泄介助】 ● 巡視・体位交換と必要に応じてトイレ介助を行う |
| 6:00〜 |
【起床介助】 ● 利用者の着替えや洗面の介助 ● バイタル測定 |
| 7:00〜 |
【朝食準備・食事介助】 ● 朝食の準備・配膳を行う ● 必要に応じて食事・服薬介助を行う |
| 8:00〜 |
【朝食片付け】 ● 朝食の下膳・口腔ケア・排泄介助を行う |
| 9:00 |
【申し送り・退勤】 ● 次の勤務者に情報共有を行い業務を引き継ぐ ● 退勤 |
夜勤16時間の給料と手当について
夜勤の16時間勤務では、通常の基本給に加えて夜勤手当や深夜割増賃金が支給されるため、収入アップが期待できます。
深夜割増賃金は、労働基準法に基づき午後10時から午前5時までの勤務に対して、基本給の25%以上を上乗せする形で支払われます。
たとえば、時給が1,000円の場合、深夜時間帯の勤務は1,250円です。
一方、夜勤手当は企業独自の制度で、支給額や計算方法は勤務先の規定によります。1回の夜勤で定額の手当が加算されるケースが多いようです。
具体的な支給額は、勤務先の就業規則や給与明細に記載されています。もし不明点がある場合は、上司や人事担当者に問い合わせるなどして確認してください。
夜勤16時間勤務の休憩時間はどうなっている?
夜勤の16時間勤務は長時間にわたるため、休憩を取って疲れを軽減させるのが重要です。
そしてしっかり休むためには、十分に休める時間と仮眠できる環境が必要でしょう。
以下では、休憩時間や仮眠スペースについて詳しく解説します。
16時間勤務での休憩時間の目安
日本看護協会のガイドラインでは、夜間の長時間勤務の場合、2時間以上の休憩を推奨しています。
16時間勤務では法律上1時間以上の休憩が必要とされていますが、実際には1時間の休憩だけでは十分とはいえないのです。
夜間の長時間勤務では、心身の疲労が昼間よりも蓄積しやすくなるため、仮眠をとることが重要です。しかし、休憩時間が1時間程度の場合、仮眠を取る時間はほとんどありません。
そのため、多くの施設では2時間程度の休憩時間を設けたり、休憩を数回に分けて確保したりと工夫を行っています。
16時間勤務を快適に乗り切るためにも、休憩時間がしっかり取れるかどうかは、重要なポイントです。
出典:日本看護協会「夜勤中の仮眠を取りましょう」
仮眠スペースは非常に重要
夜勤中にしっかりと休憩をとるためには、仮眠を取れる休憩室が肝心です。
介護の現場ではナースコールの音や、利用者さんが立てる物音などが多く、仮眠をとれる環境とはいえません。
休憩するためには、さまざまな物音に邪魔されない静かな環境が必要です。
質の高い仮眠が取れなければ、集中力や判断力が低下し、業務のパフォーマンスに悪影響を及ぼすでしょう。
それゆえ、介護の16時間夜勤業務を行うためには、しっかり休める休憩室は必須といえるでしょう。
ワンオペ夜勤は労働基準法違反?休憩なし勤務は?
介護保険施設では、夜間に配置すべき人員の基準が決められています。そのため、配置基準と労働基準法に違反しなければ、ワンオペ夜勤でも違法にはなりません。
しかし、休憩時間を確保できない場合、労働基準法に違反する可能性があります。
労働基準法第34条では、6時間を超える労働には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を取らせることが義務付けられています。
さらに休憩中は、労働者が自由に休憩時間を利用できる状態でなければなりません。
しかし、ワンオペ夜勤の環境では休憩中に対応を迫られることが多く、結果として休憩が形骸化してしまうでしょう。
そのため、休憩が十分に取れないワンオペ夜勤は、法的な問題を抱えている可能性が高いと考えられます。
出典:厚生労働省「労働基準法」
労働基準法に違反していると感じた場合の相談先
夜勤の16時間勤務やワンオペ夜勤において、労働基準法に違反していると感じた場合、適切な対応を取ることが重要です。
とくに休憩時間が確保されない、違法な勤務体制が常態化しているなどの場合、早めに相談してください。
上司に相談しても期待できない場合は、以下の場所に相談してみてください。
⚫︎労働基準監督署
⚫︎総合労働相談コーナー
⚫︎労働基準監督署
労働基準監督署
労働基準監督署は、労働基準法や労働安全衛生法などの法律に基づいて、労働環境の改善や労働者の権利保護を行う機関です。
勤務時間や休憩時間が法令に違反していると感じた場合や、過酷な労働環境で働かされている場合には、最寄りの労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準監督署に相談すれば、状況を改善するための指導や調査が行われることがあります。
相談は無料で匿名での対応も可能なため、安心して利用できます。
参考:厚生労働省「全国労働基準監督署の所在案内」
総合労働相談コーナー
総合労働相談コーナーは、厚生労働省が全国各地に設置している相談窓口で、労働に関するあらゆる疑問やトラブルに対応しています。
勤務時間や賃金、休憩時間の不備などに関する疑問がある場合でも、専門スタッフが法的なアドバイスや解決策を提案してくれます。
また、労働基準監督署やそのほかの適切な機関に取り次ぐことも可能です。
参考:厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」
労働条件相談 ほっとライン
労働条件相談ほっとラインは、厚生労働省が運営する全国共通の電話相談窓口です。
勤務時間や夜勤手当、休憩時間に関する疑問や不安がある場合、専門スタッフが直接対応し、適切なアドバイスを行います。
窓口は平日だけでなく、土日や夜間にも対応しているため、忙しい人でも利用しやすいでしょう。
相談は無料で、全国どこからでも利用可能ですので、困ったときにまず連絡してみることをおすすめします。
参考:厚生労働省「労働条件相談 ほっとライン」
職場が労働基準法に違反しているなら転職も視野にいれよう
介護職の夜勤が労働基準法に違反している場合、転職を検討するのも一つの選択肢です。
法律違反が放置される職場では改善の期待が薄く、自身の健康やキャリアに悪影響を及ぼす可能性があります。
休憩時間がない場合や、規定を超える長時間労働が常態化しているところで働き続けると、体調不良やバーンアウトに繋がりかねません。
まずは労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどに相談し、現状の改善を試みてください。相談しても改善が見込めない場合には、転職を選択肢に入れ、より良い職場を探しましょう。
健康と将来のためには、自分自身を守る選択をすることが大切です。
自分に合った職場を選ぶ3つのポイント
自分に合った職場を見極めるためには、休憩環境やスタッフ体制などを慎重に確認することが不可欠です。
ここでは、職場を選ぶためのポイントについて、詳しく見ていきます。
⚫︎勤務形態と夜勤回数を確認する
⚫︎休憩時間や仮眠室の有無を調べる
⚫︎スタッフ体制や業務量のチェックする
夜勤回数を確認する
職場を選ぶ際には、夜勤の回数を事前にチェックしてください。
夜勤は身体的・精神的な負担が大きく、回数が多いと生活リズムが乱れるリスクが高くなります。とくに夜勤の多い職場では、睡眠不足や疲労蓄積による健康への影響が懸念されるでしょう。
夜勤の回数は職場によって大きく異なります。月に2~3回程度に抑えられている場合もあれば、週に1〜2回のペースで夜勤が求められるケースもあります。
自分のライフスタイルや健康を守るためにも、応募する職場での夜勤回数については前もって確認し、納得した上で選んでください。
休憩時間や仮眠室の有無を調べる
長時間の勤務において、適切な休憩が取れるかどうかは働きやすさに直結します。
そのため、休憩時間がしっかり確保されているか、仮眠室や休憩スペースが充実しているかを見てください。
夜勤中に2時間程度の休憩が取れる職場では、体力的な負担が軽減され、勤務後の疲労感が大きく異なります。
逆に、十分な休憩が取れない職場では、長時間勤務が心身に大きな負荷をかける可能性があります。
見学や面接の際に、職場環境や休憩設備について具体的に質問しておくと良いでしょう。
スタッフ体制や業務量をチェックする
夜勤で働く介護の職場を選ぶ際、スタッフ体制や業務量を確認してください。
夜勤の人数が少ない割に多くの業務をこなさなければならないのなら、心身の負担は大きくなるでしょう。
介護施設では夜勤中に急患対応や突発的な事故が発生するケースもあるため、スタッフが不足していると1人で対応しなければならず、休憩どころではないでしょう。
そのため、面接や職場見学の際に、夜勤のスタッフ配置数や業務量などを具体的に確認することが大切です。
夜勤16時間勤務を理解し、適切な働き方を選ぼう
夜勤の16時間勤務は適切な条件を満たせば違法ではありませんが、ワンオペ夜勤や休憩不足が違法性を問われるケースもあります。
そのため、労働基準法や職場の体制を正しく理解し、自分に合った環境を選んでください。
就職活動では、休憩時間の確保や仮眠環境の有無やスタッフの体制を確認し、安心して働ける職場を選びましょう。
とはいえ、しっかりと休憩を取れるかどうかやスタッフ体制などは、なかなか外部からはうかがい知れません。
そのため、快適に夜勤が勤められる職場かどうかを見極めるために、転職サイトや転職エージェントを活用するのも、一つの手です。
ユメシア転職JOBでは、介護業界に精通したコンサルタントが丁寧にあなたの転職活動をサポートします。
転職後も仕事の悩みをコンサルタントに相談できるため、転職にまつわる不安もやわらげてくれるでしょう。
まずは、あなたの職場での悩みを相談することから始めてみてはいかがでしょうか。